はじめに:放ったらかしにしてた話題
前回予告しましたように…紙のハナシはぼちぼち終わりになりますが、1個だけ解説をしないまま放ったらかしにしてた話題がありました。
伏線回収っていうわけでもありませんが、その解説を少し…。
第1回の謎の一文
第1回の最後に『なお、 “A4判” とか “A4版” という紛らわしい漢字表記はご注文の際に使わないでいただきたいのです』 って書きました。
『ん? なんでダメなの?』って思われた先生も多かったんじゃないですか?
はい。書いた私も、そう思ってます😅
誤発注事件の顛末
いや…実は3ダース、以前に誤発注しちゃった事があるんです。
『A4規格のケント紙』を紙問屋さんに断裁で作ってもらうFAX注文用紙に…ついつい『A4判』って書いちゃったんですよ。
まさかの事実
『え? ”A4規格とA4判” って違うの!?』って思いますよね?
そうなんですよ。3ダースもまさか『JIS規格の仕上り寸法のA列4番』の他に、それとは違う『A4判』がこの世に有るなんて、知りませんでしたよ! (いや、そんなの無いはずなんですけどね😅)
いつもの注文方法
普段は『アイボリーケント#200 四六判50枚をA4規格に断裁してください (A4で550枚) 』と、長々と注文書に書いてました。 まあ、『A4規格』のところを『A4サイズ』とか単に『A4』って書く場合もありましたが…。
とにかく、原紙の枚数と寸法と…その寸法での仕上り枚数までをイチイチネチネチ書いていたのでけっこう丁寧というか…まどろっこしい書き方をしていたんですよ。 (四六判からA4規格は11面作れるので、原紙枚数 × 11で仕上り枚数になります)
運命の注文書
でも…その誤発注は、『A4』って書くべきところをついつい『A4判』って書いちゃってました😱
それに、いつもの書き方があまりにまどろっこしかったんで原紙枚数を書くのを “はしょっちゃった” んですよ、その時だけは…。 もう、同じ内容の注文をすでに何回かしてましたから…。 今回は細かく書かなくても大丈夫だろうと思って『アイボリーケント#200 A4判で550枚』ってFAXしちゃったんですね。
届いた品物に愕然
で、品物が届いた時の紙問屋さんの納品書を見て愕然としました。 原紙枚数50枚を使ってA4規格が550枚仕上るはずなのに、原紙枚数が55枚も使ってることになってる😱
しかも仕上り寸法が、見た感じA4規格より…ちょっとデカイ。 コピー用紙のA4と比べてみて、こちらの希望のサイズではない事を確信。
紙問屋に電話
で、大至急紙問屋さんに電話しましたよ。 そしたら『A4とA4判は違う大きさです』との返答。
『はぁ?😡知らん!!! そんなん知らんがな!!!』
3ダースキレましたわ!
『そんなん誰が決めた? なら、価格表の最後んとこの “資料ページ” に書いとけや! 書いとらんがな!!! JIS寸法や木枠寸法はイチイチ書いてあんのに! しかもあんたんとこの資料の木枠寸法の4号Pサイズ…何度も訂正依頼の電話かけてんのにいまだに直せてないやん! 間違ったまんまやん! そんなん間違ったまんまのサイズ書く枠があるんなら “ウチで言うA4判は何㎜ × 何㎜でございます” って書いとけや! 普通A4判言ったらJISのA4だろがっ!!!』
事務員さんには申し訳ない
電話に出てくれた事務員さんには本当に…本当に…本当に申し訳ないキレ方でしたが、紛らわしい注文だと思われる場合は断裁する前に注文主であるウチに確認してほしかったんですよ。
どうやらFAXを見た事務員さんは “社内で” 確認をしたそうな。『これA4規格ですかね?それともA4判ですかね?』って。そしたら社内の誰かが『A4判って書いてあるんだからA4判だろうが』とでも言ったんでしょう。
いや、そっちで確認するんじゃなく…ウチにかけてこいよ、電話!
だいたい何だよ “A4判” って! “判” が付いたらひとまわりデカくなるんか? 知らんぞ、そんな法則!
おたくの価格表のページにはどこ見ても『A4判は何㎜ × 何㎜』なんて書いてねぇんだから! オモテにも裏にも背表紙にも!!!
ネットにも情報なし
実際、ネット上で検索しても “規格のA4よりひとまわり大きいA4判” なんて、どっこにも出てませんでしたよ。
注文の経緯
ちなみにこの注文をしてきた先生は、以前話題にした『B全パネル2枚注文です』…って電話かけて来る先生。 今回のは『ケント紙 “A4判” で注文です。500枚くらいの、そちらの切りの良い数で』…って😅
ウチはそれをそのまま “受注ノート” に『○○高校 学校長あて アイボリーケント#200 A4判 500枚くらい』と書き、それをもとにして紙問屋さんへのFAX注文用紙にも…ついうっかり『A4判』と書いちゃったわけです。
もちろん、その先生の責任じゃありませんよ。
ウチと紙問屋さんのやり取りに、どちらも配慮が足りない部分があった…ってこと。
マジで知らんがな!
しかし、規格のA4よりひとまわり大きい “A4判” なんて…。
マジで知らんがな!
『判』って付けたらなんでもデカくなるんかい? そんなん知らんっ!!! だったら俺に “判” って付けてくれよ。170にちょっと足りてないんだから…。いくらかデカくなって、少しはマシに見えるだろうよ!
“A4判” の正体
後日、落ち着いて紙問屋さんに聞いてみたら、その “A4判” という大きさは『A本判の8切』のことのようでした。
その大きさがA4パネルに水張りするのにちょうど良いから “A4判” と呼び慣わしているそうな。
社内規定を押し付けるな
ってことは社内規定か?
だったらそんなのこっちに押し付けんなよ! しかもこっちは過去にそんな変なサイズの注文したことないんだし、頼んだアイボリーケントの#200にはそもそもA本判なんて原紙寸法は無いんだし!
(四六判から、A本判の8切に相当する大きさを “わざわざ” 切り出してくれたようです。A4規格なら四六判から11面作れるのに、その “A4判とかいう寸法” は…A4規格よりひとまわり大きいもんだから四六判から10面しか作れないため…55枚の原紙が必要になったわけです)
そんな変な寸法を四六判からわざわざ切らせるような注文するわけないっしょ! 断裁料だって取られてるのに! バ○かっ! 常識で考えろや!
紙問屋さんの想定
あ、すみません。言い過ぎました。 あれですよね。紙問屋さんも長年の経験から…学校の授業で使うケント紙だから、きっと水張りさせるんだろうって思ったんですよね? はいはい、わかりますわ。
B列の規格サイズを作る断裁ならまだ有り得ますが、ケント紙をA列規格に…20%もの面積の紙をムダにするような切り方をするワケは絶対に無いって思ったんですよね? 常識的に考えて、ケント紙や画用紙をA3やA4の規格に切り縮めるなんて…学校からの注文には有り得ないっすからね。
『まぁB3規格やB4規格ならわかるケド、A列の規格サイズの可能性は絶対に無いよ。だからきっと水張り用だ!』って思ったんでしょうね。
時代を読めていない
甘い!!! 紙問屋サン、甘いっす!
時代を読めてません!
今は、ナゼか教員のみなさんはA列で切りたがるんです。切らせたがるんです。
紙の注文はなんでもかんでもA列になっちゃってるんです。
20%捨てようが27%捨てようが、わざわざ切り縮めさせるんです。 そんな時代なんです!!!
それが、紙問屋サンにはまだ伝わってないんでしょう。
ベテラン先生からもA列注文
しかも、このA4規格550枚の注文をくれたのは若手の先生でなく、中堅~ベテランの域の先生! (B1を “B全” って呼んでるくらいですから…)
今は…どの年齢層の先生からも、A列規格の注文がジャンジャン来るんです。 そういう時代になっちゃったんです。
そのあたりを…今度機会を見つけて、じっくり紙問屋さんと話さねば…。
…と、思った次第です。
解決
結局その紙はこちらが欲しかった大きさの断裁のものと交換してもらいました。
紙問屋さんが受注時に相手に確認をしなかった…という非を認めてくれたわけです。 (当然ですわ)
使った原紙枚数も50枚ってことにしてくれて…。 (これも当然ですわ)
お願い:『A4判』と書かないで
まぁ…そんなことがありましたんで、みなさんにも『A4判』っていう言い方や書き方でご注文なさるんではなく、単に『A4』とか、逆に丁寧に『A4規格』とおっしゃっていただけると、ありがたいかなぁ…と。 (ノートに書き取ったり注文のFAX用紙に書き込む際に、ウチがうっかり『判』って書いちゃう恐れを、なるべく減らしたいんです😅 まぁ、あくまでもこちらの勝手な都合のお願いなのですが…)
そんな気持ちで、ついつい第1回の最後に変なことを書いちゃったんです。 みなさんからすると意味のわからないことを書いちゃってたわけでして、大変失礼いたしました😅
『判』と『版』の違い
なお、『A4版』の “版” は、紙の大きさを表す字としては誤字です。 “版” って書いちゃったら恥ずかしいですよ…っていう忠告の意味で書かせていただきました。
まったく違う意味
『判』と『版』を同じ意味だと思ってるヒトも世の中にはいらっしゃるようですが、全然別な意味です。
**『版』**は版画や印刷における…インクを紙面に乗せるための “もの” を指すコトバ。版木とか印刷版のこと。 また、増版 (重版) した回数を『版』の字を使って表したりします (初版とか第三版とか…) 。 ※ 加筆や修正をせずに刷り増すことは “増刷” 、加筆や修正をして改訂版を出す場合を重版と言います。
**『判』**は紙や書籍の大きさを表すコトバです。 たぶん3ダースにくっつけても身長は伸びないと思います。
また、『版』の字を使って “大きさ” を表すこともまれにありますが、この字はあくまでも印刷された “版面” の大きさを示すもので、印刷されてない紙には使えないコトバだし、印刷された紙の周りの余白部分はこの『版』の字では表すことはできません。
よって、『判』と『版』はまったく違うコトバです。
おわりに:紙は奥が深い
とにかく、うっかり注文書に『判』の字を書くととんでもないことになるかも…と、肝に銘じた出来事でした。
普段当たり前に使っている『木炭 “判” 』や『木炭紙 “判” 』にも気を付けた方がいいのかも。
いやぁ、紙って奥が深いですわ!
わからないことがまだまだたくさん有りそうです。
【第17回終わり】











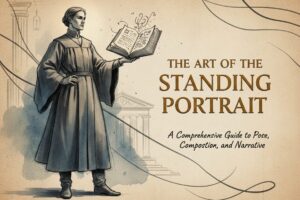



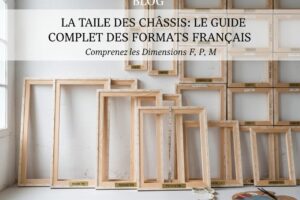
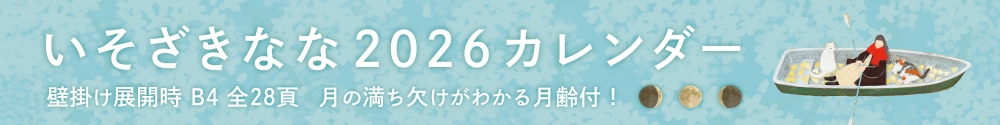





コメントを残す