平日の川越で感じた、アートと観光の交差点
2025年11月13日、江戸の面影を色濃く残す川越の街を訪れた。今年で第8回目を迎える「蔵と現代美術展2025」を観覧するためだ。今年の春、豊島区池袋で「回遊派美術展」とコラボした「FiveStar2025」の実行委員長を務めた私にとって、同じく回遊型のアートイベントである川越の試みは、大いに参考になるはずだと感じていた。
驚いたのは、平日にもかかわらず観光客の多さである。蔵造りの街並みを歩く人々の波、食べ歩きを楽しむカップル、記念写真を撮る家族連れ――川越の街は平日とは思えない活気に満ちていた。「小江戸」と呼ばれる川越は、明治26年の大火後に建てられた耐火建築の蔵が今も残り、岡山県倉敷市、福島県喜多方市と並ぶ「日本三大蔵の街」として知られている。
アーティストとの出会いが導いた川越探訪
今回の訪問のきっかけは、昨年もこの美術展に出品していた藤澤慧梨子さんからの紹介だった。多摩美術大学油画科を卒業し、世田谷美術館ギャラリーや示現会展などで活躍する藤澤さんは、旧山崎家別邸・小川長倉庫Bに作品《面 OMOTE》《花》を展示されている。
藤澤さんから紹介されたのが、田村優幸さんだ。実行委員も務める田村さんは、小川長倉庫Aに《The Spots》を展示。「気跡の経過 太陽の黒点」というサブタイトルが示すように、時間と空間をテーマにした作品は、蔵という歴史的空間と見事に呼応していた。
「蔵と現代美術展」―12年の歩みと深化
「蔵と現代美術展」は2012年に始まり、今年で12年目を迎える。当初は寄居町での試みから始まり、その後川越市内の蔵や歴史的建造物を舞台に本格化。2013年の第1回川越展から数えて、今回が第8回目の川越開催となる。
この美術展の最大の特徴は、蔵という「場」そのものを作品の一部として取り込む点にある。美術館のホワイトキューブとは異なり、蔵独特の密閉された空間、重厚な梁、漆喰の壁――これらの歴史的要素が現代アートの表現を引き立て、同時にアート作品が建造物に新たな息吹を吹き込んでいる。
今回、私が訪れたのは以下の4箇所である。
- 仲町観光案内所
- 旧山崎家別邸
- 小川長倉庫A・B
- 本丸御殿
それぞれの会場で共通して感じたのは、作品と場所との見事な調和だった。歴史的建造物という”場”が作品の一部となり、鑑賞者に時空を超えた体験を提供している。これは単なる展示ではなく、空間と作品が「響き合う」インスタレーションの醍醐味だ。
国際交流への広がり―オッフェンバッハとの絆
「蔵と現代美術展」は、地域に根ざしながらも国際的な視野を持っている。川越市と友好都市提携を結ぶドイツ・オッフェンバッハ市との文化交流プロジェクト「DISTANT VIEW(遠景)」は、その象徴的な取り組みだ。
2023年8月、オッフェンバッハの美術館で日本人作家3名とドイツ人作家4名による合同展示が開催された。異なる文化背景を持つアーティストたちが、同じテーマで作品を発表し対話する――こうした国際交流は、地域のアートイベントに新たな深みをもたらしている。
類似イベントから学ぶ―地域アートの可能性
日本には、地域を舞台にした大規模なアートイベントがいくつか存在する。
瀬戸内国際芸術祭は、瀬戸内海の12の島々を舞台に春・夏・秋の3シーズンにわたって開催され、2022年には延べ108万人が来場。経済効果は約89億円に達した。
**越後妻有アートトリエンナーレ(大地の芸術祭)**は、新潟県の越後妻有地域で3年に1度開催され、2024年には約54万人が訪れ、経済効果は約120億円と推定されている。
びわこビエンナーレは、滋賀県近江八幡市の空き家を活用した「まちなか型アートフェスティバル」として、2024年には延べ4.6万人の来場者を記録した。
これらと比較すると、「蔵と現代美術展」は規模こそ小さいものの、歴史的建造物という「場」の力を最大限に活かすという独自のコンセプトで差別化を図っている。大規模な集客よりも、質の高い鑑賞体験を提供することに重きを置いているのだ。
池袋モンパルナスからの系譜―回遊型アートの伝統
今年5月、私が実行委員長を務めた「FiveStar2025」は、「池袋回遊派美術展2025」とコラボレーションし、自由学園明日館で開催された。この「回遊派美術展」の背景には、池袋の豊かなアートの歴史がある。
1970年代初頭から1980年代にかけて、池袋を中心に展開された芸術文化運動「池袋モンパルナス」。自由学園明日館を拠点に、若き芸術家たちが集い、自由な創作活動を繰り広げた。その精神は現在も「池袋モンパルナス回遊美術館」として継承され、東京藝術大学も「池袋モンパルナス芸術祭」を開催するなど、池袋はアートの街としての伝統を引き継いでいる。
「FiveStar2025」では、IAG AWARDS入選者を中心とした気鋭のアーティストによる作品展示に加え、5つの画材ブランドが集結。ライブペインティングやクロッキーパフォーマンスなど、アートを「体験する」場を提供した。
川越も池袋も、街全体を「歩きながら」アートに出会う回遊型のイベントという点で共通している。しかし、川越が歴史的建造物を活かすのに対し、池袋は現代的な文化施設や公共空間を活用する――それぞれの街の特性を活かした展開が興味深い。
観光とアートの共存―見えてきた課題
しかし、今回の散策で感じた課題もある。それは、観光客の多さとアート鑑賞の両立の難しさだ。
展示会場を移動する際、観光客の波に揉まれながら歩くのは、正直なところかなり疲れた。食べ歩きや写真撮影を目的とする観光客と、静かにアートを鑑賞したい来場者とでは、求めるものが異なる。もちろん、意識の高い方々も見学に来ていたので、全員が無関心というわけではない。だが、もう少し多くの観光客がアートに興味を持ってくれれば、この街のポテンシャルはさらに高まるのではないかと感じた。
瀬戸内国際芸術祭や越後妻有アートトリエンナーレは、「アートを見に行く」という明確な目的を持った来場者が中心だ。一方、川越のような観光地でのアートイベントは、観光客とアート鑑賞者が混在する。この状況をどうマネジメントするかが、今後の課題だろう。
考えられる解決策としては、
- サイネージやマップでアート展示の存在を積極的にアピールし、観光客の関心を喚起する
- ガイドツアーやワークショップを通じて、観光客がアートに触れるきっかけを作る
- 混雑時間帯の分散化を図り、ゆっくり鑑賞できる環境を整える
- SNSでの情報発信を強化し、アート目的の来場者を増やす
こうした工夫により、観光とアートの相乗効果を高めることができるはずだ。
実行委員長として学んだこと
「FiveStar2025」を開催した経験から、回遊型アートイベントの成功要因について考えてきた。今回の川越訪問で、改めて以下の点が重要だと感じた。
1. 場所性の活用
川越は蔵という歴史的建造物、池袋は自由学園明日館という重要文化財――それぞれの「場」の持つ力を最大限に引き出すことが、イベントの独自性を生む。
2. 作家と場所のマッチング
すべての作品がどの場所にも合うわけではない。作家の作風と展示空間の特性を丁寧にマッチングすることで、作品と場所が「響き合う」体験が生まれる。
3. 地域との連携
行政、商店街、地域住民との協力関係が不可欠。特に、地元の理解と協力があってこそ、回遊型イベントは成立する。
4. 継続性と発展
「蔵と現代美術展」の12年、池袋モンパルナスの50年以上の歴史――継続することで地域に根付き、ブランドとして認知される。
5. 国際的な視野
オッフェンバッハとの交流のように、地域に根ざしながらも国際的な視野を持つことで、イベントに新たな深みが加わる。
おわりに―未来のアートイベントへの希望
「蔵と現代美術展2025」は、歴史的建造物とアートの共生という点で、非常に示唆に富んだイベントだった。藤澤慧梨子さん、田村優幸さんをはじめとする作家たちの作品は、蔵という空間の中で新たな生命を宿していた。
観光とアート、歴史と現代、地域と作家――これらの要素がどう響き合うか。それを考え続けることが、私たちアートイベント実行委員の使命なのだと、改めて感じた川越散策だった。
春の「FiveStar2025」では、画材メーカーと作家、そして来場者をつなぐことを目指した。今回の川越での経験は、次のイベント企画に必ず活きてくるだろう。街の回遊性を高めながら、アートへの関心をどう喚起するか――この課題は、川越も池袋も共通して抱えているテーマだ。
2025年11月16日まで開催される「蔵と現代美術展2025」。川越を訪れる際は、ぜひ観光だけでなく、蔵の中に息づく現代アートにも目を向けてほしい。歴史と現代が響き合う、唯一無二の体験がそこにある。
会場情報
蔵と現代美術展2025 ―響き合う空間―
- 会期: 2025年11月2日(日)〜11月16日(日)
- 会場: 川越市内の蔵や歴史的建築
- 仲町観光案内所
- 旧山崎家別邸
- 小川長倉庫A・B
- 本丸御殿 ほか
- 主催: NPO法人蔵と現代美術展
- 入場: 無料
- アクセス: 西武新宿線「本川越駅」、JR/東武東上線「川越駅」より徒歩
参考リンク:














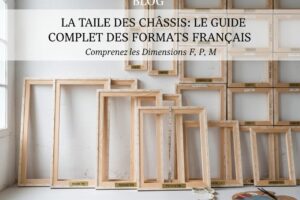
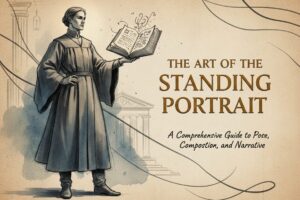

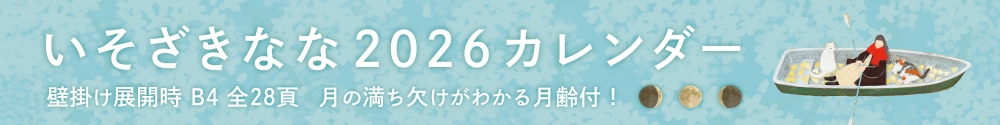





コメントを残す