前回の補足
前回、紙の組成や紙の色のハナシで終わってしまい、肝心の『画用紙とは?』『ルールや決まりはあるの?』という結論にたどり着けていませんでした。
大変失礼しました!
画用紙のルールと決まりごと
では、画用紙のルール…というか、決まりごとを見てみましょう。
画用紙の定義
『画用紙は別名 “画学紙 (ががくし) ” とも呼ばれる』
もう一つ。
『原紙寸法が、なぜか “B本判 (765 × 1085) ” で作られている』
以上です!
いやぁ、単純ですねぇ。
でもこれはけっこう大事なことなんですよ。
画用紙…すなわち画学紙は、学校の授業でしか…あるいは学生さんしか使わないってことになってます。
だから『学』の字が加わってるんです。
つまり、画用紙は学生さん達のための紙なんです。
まあ、もちろん大人が買っても罰せられることはありませんが、透明水彩を専門でやってる大人は画用紙より上のグレードの『水彩紙』を買いますしね。
B本判の謎
そして我々画材屋が扱う紙の中で…原紙寸法がB本判で作られているのは、なぜか画用紙 “だけ” なのです!
色画用紙は四六判
『色画用紙』ってありますよね?
商品名でいうと…例えば『ニューカラーR』。
みなさん、意外って思われるかもしれませんが…色画用紙の原紙寸法は “四六判 (788 × 1091) “ ですからね!
“普通の画用紙だけ” がB本判なのです。
そもそも色画用紙は『画学紙』とは呼ばれません。つまり、色画用紙っていう紙は…あくまでも**『画用紙風のいろがみ』**っていうことであって、厳密に言えば “画用紙” ではないんです。
他の紙はすべて四六判
普通の画用紙…つまり学生さんしか使わない画用紙だけが、なぜか原紙寸法がB本判。
他の『ケント紙』や『上質紙』や国産の『水彩紙』、そして『色画用紙』『タント紙』『ラシャ紙』『色上質紙』『マーメイド紙』『コットン紙』『カラーケント紙』『レザック紙』など、いわゆる美術の授業やデザイン系の “仕事” で使われる紙の原紙寸法はすべてが四六判なのに…。
何度も何度も言いますが、学生さんが授業で使う “普通の画用紙だけ” がB本判!
長年の謎を追う
3ダースにとって、これは長年の謎でした。
(気にしなければよかったんですが、気になっちゃったんです)
紙に詳しい人に会うたびに質問攻めにしても、誰一人答えてくれませんでした。
みんな『昔からそうだった』『そういうもんだ』『意味なんてないんじゃない?』という答えで…。
で、もう10年くらい前でしたが…美術用紙大手のM社に電話で聞いたところ、**『どうやら戦前の文部省のお達しによって決まったようだ』**とのこと。
でも、その詳しい解説までは得られませんでした。
以後何年も画材業界の現場で感じた事象を組み合わせて、ようやく自分なりの結論は得られたんじゃないかな…と思います。
3ダースの最初の結論
以下、3ダースの結論です。
そもそも画用紙は学生のための紙であり、大人は使わない。
プロの製図屋はケント紙を使うし、プロの絵描きは水彩紙を使うだろう。
プロはその紙で仕事をし…お金を稼ぐんだから、紙の値段が高かろうがまったく問題はない。
しかし学生は高い紙をなかなか使えないし、親の負担も大変である。よって、学生が使う画用紙だけは少しでも紙の寸法を小さくし、また規格サイズに断裁したとしても断ち落として捨てる無駄が極力小さくて済むように、四六判ではなくB本判が選ばれた…。
これが3ダースがたどり着いた結論です。
B本判とは何か?
では、そもそも “B本判” とは何なのでしょうか?
これは主にB列仕上がりの書籍や雑誌を作る際の原紙寸法のことです。
本の中身の紙…。つまり、いわゆる**『本文用紙』**と呼ばれる紙のための原紙寸法なのです。
だから、”製本” するわけでもないし “印刷” するわけでもない画用紙が、B本判で作られていることにすごい違和感があるんですよねぇ。
出版印刷とB本判
本文用紙の印刷って、前にも話しましたが…16ページや32ページや64ページ分を一度に大きな紙の表裏に印刷し、折って折って3辺を断裁する…っていう印刷方法。
こういう形式の印刷を**『出版印刷』**って言います。
出版印刷では…印刷後に断ち落とす位置も初めから決まってますし、印刷用紙の周りの部分に大きな余白を必要としないため、本文用紙の印刷には四六判なんかは使いません。四六判では無駄になる部分が多いですから…。
だから、出版印刷をメインの仕事にしている印刷工場では、四六判より少し小さいB本判の印刷用紙を使うのがセオリーなのです。
商業印刷と四六判
一方、出版印刷以外の印刷をひっくるめて**『商業印刷』**と言います。 (あと事務用印刷っていうカテゴリーもありますが、それは置いておきます)
現在の商業印刷はカラー印刷が当たり前。
チラシやパンフレットやポスターだけでなく、ありとあらゆる印刷物がカラー印刷されています。
印刷現場で最も主流のオフセット印刷は、黒・シアン・マゼンタ・イエローの4つの版を順番に重ねて刷ることで、すべての色を再現します。
現在、商業印刷で使われる原紙寸法は四六判がメイン。これは印刷用紙の周りの余白部分に、4色の版のズレのチェックや…刷り上がったあとにする断裁のための位置指定となるトリムマーク (トンボ) を刷り込むため、どうしてもB本判より大きな “四六判” が必要になるからです。
戦時中の紙規格
今でこそ四六判全盛の時代ですが、昔はどうだったのでしょう。
四六判製造禁止の時代
実は四六判での原紙の製造が政府から “禁止” されていた時代があったそうなんです!
これはメルマガのために紙のことを徹底的に調べた結果、わかったこと…。
そう、昭和初期の戦争中の頃ですね。
日中戦争が終結しないまま日本は太平洋戦争になだれ込みましたが、その頃の日本では四六判の紙を作ることが禁止されていたそうなんです。
JES規格の制定
明治時代後半には四六判の紙は国産され始め、菊判とともに国産の原紙寸法として定着しました。
昭和4年に、JIS規格の前身の日本標準規格 (JES) が定められ、仕上り寸法で『A列』と『B列』が採用され、原紙寸法の全国統一規格には新たに考案された『A本判』と『B本判』が採用されます。
でも、とっくに国産化されていた原紙寸法の『四六判』と『菊判』は “準” 規格扱いとされ、JESへの正式採用はなりませんでした。
…と言うのも、当時の四六判と菊判はメーカーによって数ミリから十数ミリのズレがあり、完全に統一された寸法というわけではなかったからなんです。
政府には、『JES制定を機に…あやふやな原紙寸法を撤廃し、原紙寸法は新しいA本判とB本判に集約してしまおう』という狙いがあったのでしょう。
そんなあやふやな菊判と四六判の製造は、しばらくの間は “黙認” されていました。
戦時体制下の無茶な指導
しかし、太平洋戦争開戦前には国の役人が製紙・印刷業界に**『断裁によって廃棄される紙が一切出ないよう、紙は製紙工場出荷時に “仕上り規格 (A1かB1) ” にせねばならない!』**と、無茶な指導をしたのです。
つまり、A1 (594 × 841) や B1 (745 × 1030) よりひとまわり大きいA本判やB本判すら今後は認めないぞ…って意味ですね。
当然、そのA本判よりさらにひとまわり大きい菊判 (636 × 939) と、B本判よりさらにひとまわり大きい四六判の製造は “違法状態” ということになります。
業界の反発と妥協案
これには製紙・印刷業界は激しく反発しました。
製紙段階で仕上り寸法に作られてしまったら、折って断裁する出版印刷はまったく成り立ちません。
また、単純な断裁で対応できる商業印刷の方でさえも、原紙の運搬中や保管中に起こりうる紙の端や角の “折れ” や “汚れ” を、今までなら周りを断ち落とせたからそんなに気にしなくて良かったものが、今後一切破損や汚損が許されなくなるわけですから…。
『せめて数㎜ずつでも大きい原紙が使えたら、少しの折れや汚れだったら…そこは断ち落とせるから無駄にならない。しかし製紙段階で仕上り寸法にするよう強制されたら仕事が立ち行かない』との必死の訴えがどうにか届き、折って断裁する出版印刷用の原紙にはA本判とB本判が存続できることに…折らずに断裁する商業印刷用には**A本判よりさらに小さい『A小判 (608 × 856) 』と、B本判よりさらに小さい『B小判 (745 × 1047) 』**という…新しい原紙寸法規格が作られることになりました。
もうこうなってしまうと、指導内容より大き過ぎる四六判と菊判は完全に禁止になり、取り締まりの対象になりました。
国粋主義者Y氏の暴走
なぜ国の役人は製紙・印刷業界を目の敵にするような指導をしたかというと、その役人Y氏は根っからの “国粋主義者” で、『余分を廃棄するような大きな紙を作るのではなく、初めからちょうどの大きさで作れ! それによって余ったパルプは軍需に回せ!』という考えだったんです。
※ 国粋主義とは、排外主義を伴う国家主義。極端な保守主義で、ファシズムとも同義と考えられる思想。
Y氏、その十数年前には製紙・印刷業界の人達と一緒に知恵を絞ってJES規格を作るために奮闘してきた仲間だったはずなのに、戦争って怖いですねぇ。ヒトの本性をむき出しにしてしまうんですよ。仲間だったヒトが敵になってしまう…。
しかしY氏、暴走しすぎでしょう?
『わざわざ捨てる紙を作るのなら、その分のパルプを軍に回せ』って。
化学繊維との関係
いったい何があったんでしょうか?
どうやら、化学繊維のハナシが絡んでるみたい。
これ、3ダースは知らなかったんですが、布を作る化学繊維ってあるでしょ?
天然繊維に対して人工で作った繊維…。
ああいう繊維って、すべてが石油由来の樹脂から作られてるんだろう…と3ダースは思ってたんですが、中には天然由来のパルプ (セルロース繊維) を化学的に合成し直して1本の長い繊維にする…っていうものもあったんですね。
パルプを原料として作られる化学繊維には**『レーヨン (人造絹糸) 』や『キュプラ (別名:ベンベルグ) 』**があって、これらはなんと…戦前から作られていたそうなんです。
繊維の分類
整理すると、繊維は大きく分けて…**『天然繊維』と『化学繊維 (人造繊維) 』**に分類出来ます。
天然繊維
“天然繊維” は『植物性繊維』と『動物性繊維』に分けられます。
- 植物性 = 『麻』と『木綿 (綿花) 』
- 動物性 = 『絹 (蚕糸) 』と『羊毛』
化学(人造)繊維
“化学 (人造) 繊維” は『合成繊維』と『再生繊維』に分けられます。
合成繊維
“合成繊維” は主に石油などから作り出した繊維で、『ナイロン』や『ポリエステル』や『アクリル』や『ビニロン』など。
再生繊維
“再生繊維” は短い天然繊維を一旦薬品で溶かし、長い繊維になるように再合成したもの。
- 『レーヨン』 = 木材パルプのセルロースが原料
- 『キュプラ』 = 綿花からとれるコットンリンターパルプのセルロースが原料
戦前の化学繊維企業
今でも存続する**『帝人』や『東レ』や『クラレ』…あと『旭化成』**って、戦前にはこのような化学繊維 (再生繊維) を作っていたんですよ。
- “帝人” = 『帝国人造絹絲』
- “東レ” = 『東洋レーヨン』
- “クラレ” = 『倉敷絹織 (のちに倉敷レイヨン) 』
ちなみに “旭化成” の旧社名は『旭絹織』。
あと…ちなみに、セロファンも木材パルプのセルロースから作るそうです。
時代背景
Y氏が化学繊維業界と癒着していた…とか、賄賂をもらっていたのでは?…と疑っているわけではありません。当時はこのように国粋主義的な考え方をするヒトがたくさんたくさんいたのです。
**『製紙・印刷業界で無駄に捨てる紙があるのなら、パルプの状態で化学繊維業界に回せ!』**って、国民の大部分のヒト達が叫んでいた時代だったんです。
製紙・印刷業界も、決して無駄に捨ててるわけじゃないのにね。
戦後の紙規格
戦後、JESは廃止され、JIS (日本工業規格…現在は日本産業規格) に引き継がれました!
JISになって、四六判と菊判は “正式な原紙規格寸法” に昇格し、A本判とB本判はJESから継続されました。
戦時の臨時規格として強制された『A小判』と『B小判』は廃止されました。
四六判が主流に
戦後しばらくの間の商業印刷は、余白の少なめなB本判とA本判を原紙寸法として使っていたのでしょうが、カラー印刷の需要が爆発的に増えてからは、余白が大きくとれる四六判の方が原紙寸法のメインの座を奪ったのでしょう。
当然、製紙工場から出荷される紙もほとんどが四六判になった…というわけです。
画用紙だけがB本判のまま
そんな中、画用紙に関しては…**『そもそも学生だけが使う紙だし、カラー印刷のような精密な印刷には使えっこない紙だから…四六判にサイズアップする必要も無いよね? 現状のB本判のままで行きましょう』**となったんでしょう。
何度か言いましたが、ケント紙はけっこう印刷用紙として使ってますし、色画用紙やカラーケントなど…さまざまな “美術用紙” は、主に商品パッケージとして使われています。
だからケント紙やその他の美術用紙は、さまざまな印刷に対応出来るよう、四六判にサイズアップが求められたのです。
しかし学校の授業でしか使わない画用紙は、印刷用の四六判にする必要はまったく無いし、断裁してもムダが少ないB本判のままでいる方が、誰の目から見てもメリットがあった…というわけ。
B本判のままで居続けたのは当然と言えます。
真実の結論
どうやら、先程述べた “3ダースがたどり着いた結論” は、間違っていたもようですね!
そもそも、画用紙は値段の高い紙ではないし、親の負担云々というほど家計に影響はありません。
実際、四六判からB本判に小さくしたところで販売価格なんて変わりません。
おそらく四六判での紙の製造が禁止されて以降、画用紙はB本判で作られていたのでしょうが、四六判が合法化された後でも…四六判にサイズアップする意味も必要も無かったため、B本判の寸法のまま現在に至った。
これが真実ですね。
最終結論
ということで、結論。
画用紙はみずから画用紙と名乗り、B本判の大きさで作られているものが、”正統派の画用紙” 。
B本判でなく、四六判とかで作られているものは “ナンチャッテ画用紙” 。
でも…たとえ正統派の寸法の画用紙であっても、まっ白過ぎる画用紙には要注意ですよ。
なるべく無蛍光のナチュラルな画用紙を選びましょうね。
【第12回終わり】


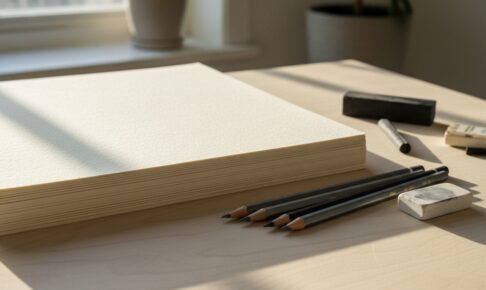










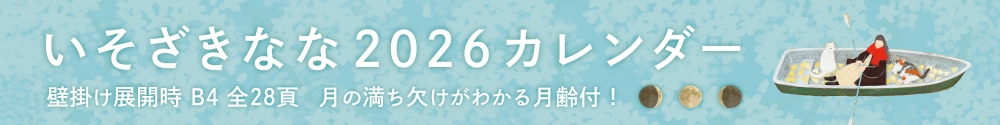





コメントを残す