またまた、サクラクレパスのハナシ
第34回と第36回で、サクラクレパスさんというメーカーのハナシをしました。
それに対して『サクラっていう会社の正式名称がサクラクレパスだって、初めて知りました』というご感想や『クレパスって、クレヨンとどう違うんですか?』というご質問が寄せられました。
みなさん、意外にこういうことをご存知ないんですね
それらのご質問に『次回かその次の回に詳しく説明します』と返信していたものの、経済学のハナシやキャンバスの手張りのハナシに力を入れ過ぎてしまい、なかなかサクラクレパスのハナシに移れずにいました。
と言うことで、今回はひたすらひたすらサクラクレパスのおハナシです。
まず、サクラクレパスさんっていう会社のおハナシから。
1921 (大正10) 年に東京にて創業 (現在の文京区小石川) 。創業時の社名は『日本クレィヨン商会』。
小学校などの教材用のクレヨンの製造販売からスタートしました。
創業者は小学校の元教師・佐竹林蔵さん。輸入品しか無かった当時のクレヨンに無限の可能性を感じ、学校を退職し…クレヨン製造に没頭。
サクラよりも少し早くからクレヨンを作り始めていた国産メーカーも有ったようですが、現在も存続しているメーカーではサクラが最古のクレヨンメーカーということになります。
後に『桜クレィヨン商会』に改称。
1923年の関東大震災後、大阪市に移転。
1924年には油絵具の製造販売も始めます。
そして1925年、世界初の画期的画材『クレパス』を発明!
1928年には水彩絵具も製造し、総合画材メーカーとして始動しました。
1950年、現在も販売されている『サクラマット水彩』を開発。
1970年、社名を『サクラクレパス』に改称。
1973年には画期的な全芯色鉛筆『クーピーペンシル』を発売!
(これはフランスの文具メーカーとの共同開発です)

今でこそ同様の商品は各メーカーで作っており、“ミリペン” や “製図ペン” などと呼ばれていますが…それらのさきがけはサクラのピグマなのです。
ピグマは “世界初の顔料インキのサインペン” とされています。従来の染料インキに比べて圧倒的な耐光性です。
水性でありながら乾けば耐水性。
なお、ピグマの太さを表す『003・005・01・02・03・04・05・08・1・2・3』は、線の太さを “㎜” で表しているモノではありません。その証拠に “小数点” が無いでしょ?
あくまでも “番号が振られた呼び名” であり、順番を表す役目は担っていますが、線の太さを正確に表した数字ではないのです。まあ、おおよその目安っていう程度でご理解ください。悪しからず。
あと、おそらくみなさんはパイロットインキやゼブラの商品で慣れ親しんでいらっしゃるかもしれませんが、“水性ゲルインキボールペン” はサクラクレパスが世界で最初に開発したんです。

そして3ダースがここ十数年間で最も驚いた新商品。『サクラポスターカラーEX』!
2011年に発売されました。
『サクラポスターカラーEX』=『ターレンスポスターカラーTPN』
ウチではサクラクレパスの子会社であるターレンスジャパンさんのブランドの商品『ターレンスポスターカラーTPN』として扱っています。

そもそも、従来のポスターカラーには2つの大きな欠点があったため、多くの先生方はポスターカラーからアクリルガッシュへと教材を変更なさいました。
その欠点とは…『重ね塗りをすると下の絵具が溶けてしまうこと』と『作品制作後の画面に水滴が垂れると…画面に輪染みが残ること』の2つ。
そのため学校現場でのポスターカラーの居場所は減り続け、ついにポスターカラーは一部のプロしか使わない…特殊な絵具ってことになってしまいました。
例えばジブリアニメの背景を描く人とか、お店の店頭ポップを書く職人さんとか、今でも手描きで作品を描くイラストレーターさんくらいしか使ってくれない絵具になってしまったんです…。
しかし、ポスターカラーEXの登場で…『乾きが速過ぎるとか固まったパレットや筆の手入れが大変』と、アクリルガッシュに移行したもののその使いづらさを嘆いていらっしゃった先生方は…ポスターカラーに戻って来つつあります。

重ね塗りしても下の絵具は溶けません。かと言って耐水性絵具になっちゃったわけではないから固まった筆やパレットも水洗いだけで対応できます。
そして作品に水滴を垂らしてしまっても、その水滴は見る見るうちに吸収・分散し、何事も無かったかのように乾燥してしまいます。輪染みはどこにも現れません。

同様の特徴を持ったポスターカラーはホルベイン (ポスターカラープラス) やニッカーからも発売されていますが、勘の良い人ならおわかりでしょう。
それらすべての製造元はサクラクレパスなのです。
ホルベインやニッカーに、サクラがOEMで絵具を提供しているんです。

ちなみに、ポスターカラーの老舗であるニッカーは、現在サクラクレパスの傘下に入り…サクラの子会社となっております。
ニッカーでは、サクラ製のポスターカラーEXは『ニッカー fun! ポスターカラー』として販売し、従来のニッカー製ポスターカラーは40mlのビンと20mlのチューブで『ニッカーポスターカラー』として今でも健在です。『デザイナースカラー』も20mlチューブで存続しています。
さて、ハナシはサクラクレパスの商品に戻りますが、ある業界で圧倒的なシェアを誇るスグレモノ商品があります。

美術教材カタログにはリトグラフ版画の用具としてソリッドマーカーが一部掲載されていますが、この商品が最も使われている現場は…造船所や鉄工所・鈑金工場・自動車整備工場・建築現場や工事現場などです。
ソリッドマーカーは…過酷な状況下での使用に耐えられる、超高性能のペンキ調マーカーなのです。
以上のように、様々な画期的商品を生み出して来たサクラクレパスの原点である『クレパス』に関して、ちょっと深掘りしてみましょう。
クレパスとクレヨンの違い
まず、クレパスってなんでしょうか?
クレヨンとは違うものなのでしょうか?
『同じものを、別な名前で呼んでるだけでしょ? 縦笛とリコーダーとか…サックスとサキソフォンとか…コントラバスとダブルベースみたいな感じで…』なんて思ってるヒトも居るようですが、そうではありません。
『同じものが地方によって呼び方が変わるんでしょ? 東京ではクレヨン。クレパスは関西特有の呼び方…』
これは面白い視点ですね。でも…気持ちはわかりますがこれも間違いです。

幼稚園や小学校の先生でさえも、このことを正しく理解している人は少ないでしょう。
読者のみなさんも、『油絵具とアクリル絵具の違い』や『アクリル絵具とアクリルガッシュの違い』や『アクリルガッシュとポスターカラーの違い』や『ポスターカラーと水彩絵具の違い』や『水彩絵具とカラーインクの違い』などは明確にご説明できるでしょうが、クレパスとクレヨンの違いを明確にご説明出来る先生は少数派だと思います。
『カタチとか、硬さじゃん?』
『はい。お見事、大正解!』
そう。カタチと硬さが違いますよ。
まず、クレヨン。こちらは先端が細く作られています。そして、クレパスと比べると硬いです。
一方のクレパスはただの円柱形。そしてクレヨンと比べると軟らかいです。

クレヨンの先端が細くなってるのには2つの理由があります。
まず、クレヨンは『線描き』に適しているため、色鉛筆のように先を削ったカタチで売られているのです。
もうひとつの理由は、クレヨンはもともとロウソクを作る金型を転用して作られていたという経緯がありますので、いわゆるロウソクのカタチを踏襲しているとも考えられます。
(貼付画像参照)
一方のクレパスは、面塗りに秀でています。
もちろん先を尖らせれば線も描けますが、尖らせても軟らかいのですぐに削れてしまい、円柱形に戻ってしまうでしょう。
ちなみに、クレヨンは面塗りにはあまり向きません。硬いので…。
あと、クレパスとクレヨンでは発色が違います。
これは単にカタチや硬さだけでなく、成分の違いに由来するものかと思われます。
クレヨンは少し透明感のある色です。黄色のクレヨンを白い紙に塗ってみればわかるでしょう。黄色がほとんど目立ちませんよ。
これは、クレヨンの成分のほとんどがロウだからです。
クレヨンに含まれる顔料だけでなく、ロウも一緒に紙の上に乗っかるわけですから、どうしても透明感のある色になってしまいます。
一方のクレパスは、ベットリと不透明に紙を塗り潰せます。
黄色同士で比べてみれば、クレパスの発色の良さは圧倒的です。
クレパスの主成分も、もちろんロウです。
しかし、顔料の濃さがとても濃いのでしっかり色が着くのです。また、ロウを軟らかくさせるための油脂が含まれていたり、クレパスの成分が紙に乗っかりやすくなるように…クレパス自体が簡単に削れてどんどんカスが出るような原料配合になっているんです。
また、クレヨンは塗り重ねがとてもしづらいのですが、クレパスでは簡単に塗り重ねができます。
クレヨンの主成分のロウは、他の色を重ねようとしても滑ってしまって乗りづらいんです。
一方のクレパスは、先程述べたように簡単に削れてカスが出るので、それが画面に引っ掛かって定着し、しっかり色が重ねられるんです。
混色も、クレヨンではほぼ不可能ですが…クレパスではよく色が混ざりますよ。
重ね塗りをする時に、意図的に下の色をめくるようにクレパスを擦り付けながら色を重ねると、うまいこと色が混ざってくれます。
これも、削れたカスが自由に動いてくれるからにほかなりません。
また…指やティッシュなどで画面をこすって色をぼかすことも、クレパスなら可能です。
クレヨンでは、ぼかしは不可能です。
これも、クレパス特有の削れたカスの存在が大きいですね。
クレヨンの顔料は…画面に定着したロウの中に留まっていますが、クレパスの顔料は…カスとともに自由に動けるのです。
クレパスとクレヨンの違いは、こんなにも大きいものだったのです。
クレパスは大人も楽しめる!!
こうして見ていくと、クレパスは幼児用の画材という枠に収まらず、大人にとってもすごく魅力的な画材と言えます。
事実3ダースは…『クレパスこそ最も手軽で最も奥深い画材』と考えております。『油絵具を超える画材だ』とさえ思っています。
ですから大人こそ、クレパスと真剣に向かい合い…クレパスの持つポテンシャルを最大限引き出すべきなのです。
大人であれば、クレパスを用いて最高の作品を描けるハズだ…と思っています。
『いやいや、クレパスなんて極めて幼稚な画材だよ。画用紙がすぐに汚くなるじゃん』って思う方もいらっしゃるかも知れませんが、そんなことはありませんよ。
確かに…子供が使うと、クレパス画は汚れやすいです。
仕上がりが汚くなります。
むしろクレヨンの方が、汚れづらいだろうと思います。

頭使おうよ。
汚さないように描けばいいだけじゃん?
画用紙が汚れるのは、何度も言ってますが…クレパスの削れたカスが画用紙の上に散らばるからです。
そんなの、ネリゴムでちょいちょい拾えばいいだけじゃん。
画用紙に定着しちゃう前に…。
あと、手のひらの…小指から手首にかけての “側面” についたカスも、画用紙を汚してしまうでしょう。
でもそんなの、ティッシュを手の下に敷けば解決です。
濃いめの鉛筆で絵を描く時も…手のひらの側面で画面を汚しちゃいますよね?
でもみなさんはそういう時にちゃんとティッシュを使ってるじゃないですか?
だったらクレパスにも応用すればいいだけのこと。簡単なことでしょう?
あと、画面にすでに乗っかってる色と別な色のクレパスを使って描くと、当然そのクレパスの先端に画面の方の色がくっついて来てしまい、その汚れたクレパスを無意識に使い続けると…クレパスの先端から別な色が画用紙に着いてしまって、想定外の色の出現に戸惑う…ということも起きるかもしれません。

(これはソフトパステルで絵を描く時の基本でもありますから、みなさんご存知でしょう)
油絵を描いてる時も、筆先が画面上の未乾燥の絵具を拾ってしまったら、みなさん筆先をボロキレやティッシュでぬぐってるじゃあないですか。
同じようにすれば、クレパス画の画面は汚れませんよ。
子供とは違い、我々大人は削れたカスの処理のしかたを知ってます。
ネリゴムを使う。
ティッシュを敷く。
クレパスの先端の汚れは常にティッシュでぬぐう。
クレパスを触る指先も常に汚れるわけですから、クレパスを持ち替える時にネリゴムをいじって、意識的に汚れを取り去るようにしましょうよ。

簡単なこと。
このように、クレパスの最大の特徴である削れたカスを…画面の汚れとして残さないように気を付けて描けば、油絵に近いタッチの重厚な絵を描くことも可能なんです。
ぜひみなさんもクレパス画にチャレンジしてみてください。
次は、クレパスの発明の経緯のおハナシです。
もともと、大正時代のクレヨンは現在のクレヨンより遥かに硬いものでした。
今でも輸入品のクレヨンなどには驚くほど硬いモノがあります。
子供が指にはめたりして遊ぶ “指はめクレヨン (フィンガークレヨン) ” なんて、ほとんどプラスチックみたいな感じですわ。つまり硬過ぎて、ろくに描けません…。
国産され始めた頃のクレヨンも、そんな感じの硬いクレヨンばかりでした。
ですので、その頃のクレヨンは “硬質クレヨン” と呼ばれています。
サクラクレパス社は、もっと軟らかくて描きやすい…まだこの世には存在しない “軟質クレヨン” を独自に開発しようと奮闘していたのです。それも、創業直後から…。
他社よりも良い商品を…他社よりも一歩先行く商品を作ろうと考える社風だったからこそ、さまざまな “発明品” を生み出せたんですね。
ロウに油脂を混ぜれば軟らかくなる…という知見は既にありましたが、ただ油脂を混ぜただけでは思ったモノは出来ません。
当時…クレヨンメーカーは雨後のタケノコのように、やたらたくさん出現していました。
みなさんご存知の…化粧品の『資生堂』や絵本で有名な『フレーベル館』も、クレヨンを作っていた歴史があります。
しかし当時のサクラだけがクレパスを開発出来たのには、ちゃんとした理由があるんです。

油絵を専門に学ばれた先生なら体質顔料をご存じでしょう。
油絵具に入っている、独特の成分ですね。
ご存知ない方のために詳しく説明しますが、現在の油絵具は油 (乾性油) と顔料だけを混ぜて練ったモノではありません。
油絵の技法が開発された当時の油絵具は、油と顔料を混ぜて練っただけのモノだったと思います。その頃の油絵具は、ユルユルの液状でした。
ダ・ヴィンチのモナリザなどは絵具の盛り上げなどまったくなく、とても平滑な表面のはずです。
やがて、さまざまな混ぜ物をして絵具に “可塑性” を持たせ、盛り上げなどが可能になりました。
その役目を担った物の一つが『体質顔料』という物質です。
(他にも…粘り気を増した加工乾性油なども、絵具に可塑性を持たせる役目を担ったと思います)
体質顔料というモノは…色を出すための顔料とは別な、流動性や粘度の調整…強度や光沢の調整…そして盛り上げや増量剤としての役割りを担う “粉末” のことです。
見た目は白い粉ですが、油と混ぜると透明なゼリー状になるんですね。
タルク (滑石の粉) や炭酸カルシウムや硫酸バリウム、雲母やシリカなど、いろいろなモノが体質顔料として使われます。
油絵具に最もよく使われていたのはアルミナホワイト (酸化アルミニウム) という体質顔料で…最も透明製が高かったらしいのですが、今は顔料の製造元がアルミナホワイトを作るのをやめてしまったため…使われていないそうです。
体質顔料を混ぜることによって、油絵具はあれだけの固さや重さを持ち得るのです。
他のどの種類の絵具とも違って、油絵具だけはチューブから押し出すと円筒形のままのカタチで絵具が出てきますよね?
アクリルガッシュや水彩絵具では、円筒形どころか…ユルい液状の絵具が出てきますでしょ?
全然違うんですよ。
体質顔料の有無が、絵具の可塑性や固さに大きな影響を与えるんです。
その体質顔料を…油脂と一緒にクレヨンの原料に混ぜてみたら、狙っていた軟質クレヨンを遥かに飛び越え、もっと軟らかい『クレパス』が生れた!…というわけなんです。

つまり、クレヨンよりもはるかに軟らかくて削れやすく、ボロボロ出てくるカス。
そのカスの “正体” が体質顔料ってことですよ。
油絵具の製造も行っていたサクラだからこそ、クレパスを生み出せた…って言えるのです。
他のクレヨンメーカーは油絵具の製造などはしていなかったので、体質顔料をクレヨンに混ぜるなんてアイディアなんか浮かびっこありません。
画材に軸足を置いていたサクラだけが、究極の画材『クレパス』を生み出せたのです。

サクラだけが使える『登録商標』です。
やがて、他のクレヨンメーカーも、クレパスを真似して作ろうとしましたが、サクラほどの品質のモノは作れませんでした。
サクラはそういう粗悪な商品に…登録商標の『クレパス』という名前を使われることを嫌い、商標の無断使用は徹底的に叩き…許しませんでした。
ですので、他社の作ったモノはクレパスではありません。一般名でオイルパステルと呼ばれます。
戦後になって、それまで硬質クレヨンを作っていたメーカーも…クレパスの良さをクレヨンに取り入れた『軟質クレヨン』を作れるようになり、現在国産で作られているクレヨンはすべてが軟質クレヨンになっております。

ぜひみなさんも…クレパスを見直し、正面から向き合ってみてはいかがでしょうか?
【第42回終わり】

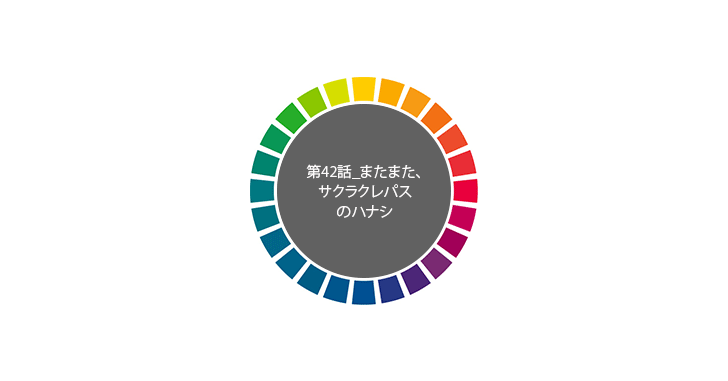

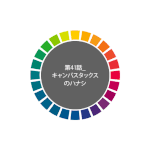

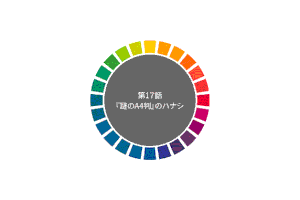

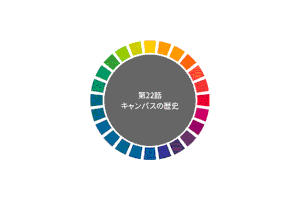




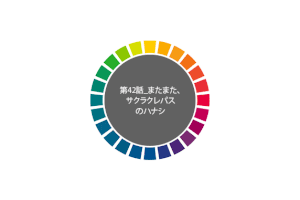







例えば『ピグマペン』。