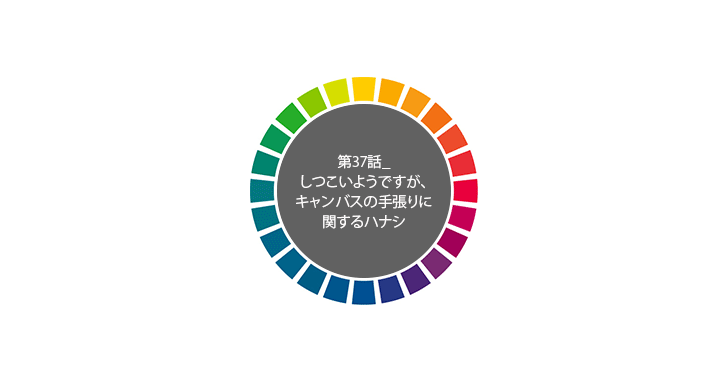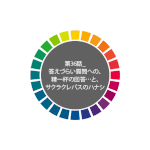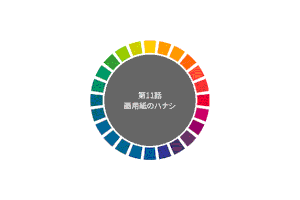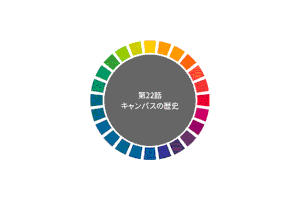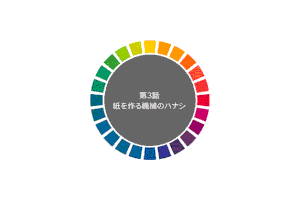しつこいようですが、キャンバスの手張りに関するハナシ
先生方から “キャンバスの手張り” に関するご相談を受けた時、3ダースはまずこう答えます。
『結局トータルで見たら、機械製の “張りキャン” が一番安いです』と…。
つまり、『部で使うお金をケチりたいから手張りをしたい』っていう考え方なら、手張りはしない方がいいですよ…と。
そうでなく…『張る楽しさを部員さんに伝えたい』っていう考え方なら、見えないコストも色々あるし…クリアーしなければならない問題もあるし、なかなか大変ですよ…と。
機械製の張りキャンなら買ってすぐ使えますし、さまざまなコストを考えれば張りキャンが一番安いのは間違いありません。 (3ダースは経済学部卒です)

張りキャンを選ばない先生は『張りキャンが一番安いだなんて…そんなはずはないでしょう』と3ダースのことを疑い、あれこれ工夫して手張りを実践されていますね。
いや、それもまた “有り” ですよ。良いと思いますよ、工夫するのは…。
それに、3ダースは生徒さんによるキャンバスの手張りを…アタマっから否定しているわけではありません。
むしろ生徒さんによる手張りは、応援したいと思っています。
でも、すべての学校で手張りをやってほしい…なんて思いません。
ウチを使ってくれてる先生だけでなく…よその業者を使ってる学校も含めて全体を見回せば、手張りをやってほしくない学校の方がはるかに多いですね…。
機械製の張りキャンから剥がした白い木枠を使い回したり…機械製の張りキャンから抜いた丸頭の釘を使い回したりするような、キャンバスの手張りに関する基本的な常識を “ご存知でない学校” には手張りをしてほしくないです。
また…木枠のオモテ裏を逆にしてキャンバスを張ってしまったり、ユルユルに張られたキャンバスを張り直そうとすら思わないような学校にも…張ってほしくない。

運転免許も持ってないのに、公道で大型バスを走らせちゃうくらい無理がある行為なのです。
一方、ちゃんとした手張り用の木枠を使い…ちゃんとしたキャンバスタックスを使って、木枠のオモテ裏の見分け方も事前に生徒さんにしっかり教えられ…張りがユルかったなら何度でも何度でも張り直しをさせ、生徒さんが満足できるようなキャンバスを作ることを…顧問の先生も一緒に目指しているような学校ならば、今後もキャンバスの手張りを存分にやっていただきたい!
3ダースも応援いたします!
もちろん、生徒さんが二人掛かりで1枚のキャンバスを張るのではなく、そのキャンバスを使う “本人” が『一人で』張ること!
これも大事な条件ですね。
“変な二人羽織” で張らせている学校は、もう二度と手張りをしないでいただきたい。二人掛かりで張っている限り、マトモなキャンバスは絶対に作れません!
なぜなら…仮に一方の子が張り具合に満足が出来ていなくても、張り直しをするにはパートナーの手伝いが必須なため、相手の絵画制作時間を奪うことになってしまう “張り直しの手伝い” を…パートナーに頼むことをためらってしまうからです。
つまり、キャンバスは必ず一人で張らねばならないのです。
自分一人で張れば…理想の張り具合を追求できますし、何より自分のキャンバスに愛着も湧きます。
しかし、あちこちの学校からうかがう “手張りの実態” は…3ダースの考えている “手張りの理想の形態” とまったく異なることが、だいぶ前に判明しました。
手張りをされている学校の、木枠の持ち主は『美術部』なんですね?
3ダースの考えている手張りの理想の形態では、木枠の持ち主は『生徒さん本人』。
例えば文化祭や高美展に大きめの作品を出品するつもりの生徒さんなら40号か50号。そして、小振りな作品も描くのなら10号とか20号…。
その木枠を個人で所有し、3年間 (実質2年半) その木枠を使ってキャンバスを手張りして描く。
木枠の裏にはもちろん自分の名前をマジックで書き、部で購入したロールキャンバスから布を切り出して手張りする…。
これが、普通だと思ってました。
で、仕上がった作品が自分でも満足がいく出来だったのなら、キャンバスは剥がさず…その作品は自宅に持ち帰り、家に飾ってもらう。
額縁は、最寄りの画材店で…親に買ってもらう。
そして、次の作品用には新しい木枠を個人で買い足す。
張って描いた作品が満足がいかない出来だったのなら…潔くキャンバスを剥がし、その木枠を使って次の作品用にキャンバスを張る…。

3ダースはそう思いますけど。
でも、ほとんどの学校で採用している方式は、『木枠は “美術部” が所有し、部員はそれを借りてキャンバスを張る』という形態。作品の展示が終わったら、キャンバスを剥がして木枠は “美術部” に返却…。
たしかに、金額が大きい木枠を…生徒さんの負担にすることを避け、部が木枠を所有することで全体のコストダウンを図っているんでしょうが、これ…生徒さんにとって何一つメリットありませんよ。

だって、生徒さんが精魂込めて描いた作品、剥がしちゃって、どうやって持って帰るの?
巻いて?
で、それを親にどうやって見せるの?
広げて?
で、どうやって飾るの?
壁に画鋲を使ってダイレクトに貼るの?

キャンバスに油絵を描いたのに、剥がして巻いて持って帰るなんて…。俺、聞いたことないよ。

確かに…巻いてあっても、再び木枠にうまく張れれば…ちゃんと額装して飾ることも可能かも知れないけど、画材店とかで新しい木枠を買ったとして誰が張るの?
キャンバスプライヤーを持ってる生徒さんなんていないよ?
画材店に絵の描かれたキャンバスを持ち込んで、そこで買った木枠を使って…店員さんに絵を張ってもらうことを頼めるかもしれないけど、けっこうな出費になるよ?
それに…巻いてある作品の張り直しは、我々画材店は基本的にやりたがりません。
ちなみに、この半年の間に二組のお客様から『巻いてある絵画を新しい木枠に張り直してほしい』という依頼が当店にありましたが、どちらの依頼もお断りしました。
『ちょっとウチでは手に負えません。よそを当たってください』と…。
その “巻かれた絵” が、とてもとてもキレイに張り直せるような状態じゃなかったからです。
巻きがキツキツで、広げることすら難しいんですから…。
ところでみなさん、絵 (油絵) が描かれたキャンバスの正しい巻き方、ご存じかしら?
『絵の面が外になるように』巻くんですよ。
つまり、ロールキャンバスの状態とは逆にするんです。
これ、知らない先生が多いんですよ。
絵の面を内側に巻いてしまったら、広げて張る時に画面がすべて割れてしまいます。
もう、無惨ですよ。
でも…ちゃんと絵の面が外になるように巻いてあれば、その被害は…ゼロには出来ませんが被害を少なく抑えられる可能性はあります。
少なくとも、後で木枠に張り直す考えが有るのであれば、“絵の面を外にして、なるべくゆったり巻く” という事は絶対条件です。
でもこれ、み~んな知らないのよね。

それに、高美展に出品してた作品なら、3ダースが余分なみみを容赦なく切り落としてしまった可能性が大ですので、木枠から剥がしたら最後…その絵を新しい木枠に張ることは誰にも出来ないでしょう。
また、木枠を所有しているのが部ってことは、誰も木枠のメンテナンスをし・な・い…ってことですよね?
個人所有で…何度も自分自身で張り替えている木枠だったなら、張る時に不便を感じる “本人” が…自分自身でメンテナンスをするかもしれませんが、部の持ち物であれば誰もしないんでしょ?。
だってどの学校も、美術部所有の『仮縁』すらも…ちっともメンテナンスしてらっしゃらないんですからねぇ。

用具や備品のメンテナンス能力が高い部活は…例えば茶道部や華道部。
あと、調理をしたり食品を作る部活 (フードなんとか部) とか、科学部 (化学部や天文部や生物部) も用具や備品のメンテナンス能力は高そう。
山岳部やワンダーホーゲル部は、用具管理をおろそかにしたら命に関わりますし…。
吹奏楽部も、木管楽器のメンテナンスは専門業者に依頼するんでしょうが金管楽器の分解洗浄なんかは業者を呼ばずに自分達でやってる学校もあると聞きます。ある程度の調律や調整は経験の有る部員ならわけもないことでしょう。
演劇部だって、小道具や衣装の使い回しをするのなら、補修や洗濯も当然するでしょう。

しかし、美術部員さんは…木枠のメンテナンスはもちろん、仮縁のメンテナンスもなさらない。

『ちょっと3ダースサン、私たちだってちゃんと生徒に筆やパレットの手入れをするように言ってます。メンテナンス能力が低いだなんて言わないでください。失礼ですよ!』って声が聞こえて来そうですが、個人管理の画材の手入れをやるのは当たり前のハナシです。
運動部員が、個人の練習着を自宅で洗濯してるのと同じ。
そんなこと、やって当たり前なこと。
今は、“部の備品” である木枠や仮縁の管理がちっとも出来てないですよね?…ってことを言ってるんです。
木枠を使った部員さんが…キャンバスを剥がして木枠を美術部の備品置き場に返却する際に、釘穴やネジ穴を埋め木したり…ササクレを丁寧に削ったりして原状復帰 (げんじょうふっき = 借りる前の状態に戻すこと) してますかぁ?
させてますかぁ?
してないですよねぇ。
させてないですよねぇ。
仮縁から作品を外した時、仮縁の内側にこびりついた絵具による汚れを丁寧に取り除いたり…拭き取ったり…洗浄したりしてますかぁ?
させてますかぁ?
してないですよねぇ。
させてないですよねぇ。
横ビス式の仮縁なら、正規のネジが常に充分な数…揃っているか、コーナー金具が曲がったりしていないか、普段から点検してますかぁ?
させてますかぁ?
してないですよねぇ。
させてないですよねぇ。
言っときますが、メンテナンスは顧問がやる仕事ではないですよ。部員が責任を持ってやることです。
もちろん、その指揮や指導は顧問が執りますが、実際にやるのは部員ですよ。
他の部活の部員さんをご覧くださいよ。当たり前に出来てるんです。
なぜか美術部員だけが、メンテナンスをやらないんです。

先生方はその自覚、有りますか?
木枠購入の初年度は、キズひとつ無い…新品の木枠ですわ。
でも毎年毎年、メンテナンスもされず…著しく劣化していくわけですから、3年後や5年後の木枠で張ったキャンバスは初年度に張られたキャンバスより確実に品質が劣化してるんですよ。
『3ダースと、3ダースが尊敬する先輩格の業界人 “K氏” との対話』 (第26回:3月9日送信) を思い出してみてください。
メンテナンスもせずに劣化した木枠をダラダラ使うのなら、部員さんたちは数年前の先輩よりも劣ったキャンバスを使わされることになります。これが “学年間格差” です。
それを何年も何年も『無自覚に繰り返してる学校がある』なんてK氏が聞いたら…あのヒト暴れ出しますよ!
K氏、正義感が強過ぎるのか…格差とか不公平とかで “弱者” が発生することにえらく敏感で、キレると手がつけられません。
普段は温厚なんですが…。
まあ、メンテナンスの指揮・指導を怠っている顧問にも、責任はあるでしょうね。
木枠は何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も使えるっていう “幻想” を信じちゃってるんだから仕方ないか…。(これ、まるで宗教ですよ)
顧問には木枠の劣化が見えてないのかなぁ。
見えてないんでしょうね。(そのあたりも、まるで宗教…)
このメルマガの読者さんには、こんなイカレた顧問はいらっしゃらないと思いますが…。
メンテナンス不足
3ダースも…去年の高美展搬出時に、過去最高に劣化した木枠を目撃しました。
ウチを使ってくれてる…ある新任の先生の学校から “搬出のみ” の運搬を依頼されましてね。
つまり、搬入直前まで描かせたいから搬入は自分達で自己搬入する…と。
で…搬出の日に、美術館から持ち出して来た作品を生徒さんから受け取った時…横ビス式のC‐40仮縁のネジ穴からネジが1本飛び跳ねたんです。
それを拾って3ダースは不思議に思いました。
そのネジの長さはほぼ20㎜。メーカーが付属させてる25㎜のネジよりは短いけど、抜け落ちる程の短さではないハズ。
20㎜あれば…少なくとも木枠には6~7㎜はねじ込まれているはずなのに、ちっとも木材に噛んでなかったような “飛びっぷり” でしたから…。
持ち帰ってその学校の仮縁を分解してみて仰天!
木枠はおそらく10年以上使われているような感じで、釘穴は同じ箇所に無数に空いているだけでなく…横ビス仮縁のネジが刺さるべき木枠の部分がゴッソリとえぐれていて、その部分には『木材』が無いんですよ。
つまり、キャンバスの側面部分のキャンバス布をペロリとめくってみたら、2㎝四方くらいの大きな窪みが空いちゃってるの。
アスファルトの下の地盤 (路盤) が大規模に逸失し、巨大な穴が道路上に出現した『博多駅前道路陥没事故』を思い出す程の…木材の逸失っぷりでした。
(2016年に起きた事故ですが、この事故をご存知無い先生は事故名で検索していただければ…当時の事故現場の画像などが見られると思います)
なぜ横ビスの位置の木材がこれだけえぐれてしまったのか…。
最初はシロアリを疑いました

『メンテナンス不足』です。
それに耐用年数をとっくに経過していた…ってことです。
常にメンテナンス (修繕と点検) をしていればここまで劣化はしません。ただ、メンテナンスの手間 (コスト) は年を追うごとに増えていきますから、ある時をもって…木枠の買い替え (更新) をしなければなりません。
木枠の更新をすべき時期の見極めも、普段からメンテナンスをしてさえいれば…おのずと分かるものなのです。
おそらくこの学校の木枠は5年経ったあたりで更新すべきだったと思います。
もともとその学校に長~く勤務していた顧問が、おそらくDIYの知識も経験もまったく無いまま、また油絵の知識もキャンバスや木枠に関する知識も持ち得ないまま、メンテナンスもせずに木枠を酷使し続けたのでしょう。
(日本画が専門の女性の顧問だったようです)
メンテナンスを指揮・指導できる能力もないため、更新されずに…使いモノにならない木枠を何年も何年も、部員さんたちは “使わされてた” んですね。
ホント、気の毒です。
その…無能な顧問が異動してから1年ごとにショートリリーフのように先生が入れ替り立ち替りされ、その間には新しい木枠に交換されることもないまま…木材の侵蝕がさら進んで行ったのでしょう。
ひょっとして…同じ規格の木ネジを使い続けていたのなら、同じ穴にウマイこと入って…穴の巨大化は防げていたのかもしれません。
でも、その…日本画の女性の顧問の時代に、正規の木ネジとは全然違うネジに交換されてしまったようなんですね。
木ネジとよく似てますがタッピングという別なネジに…。
このタッピングネジは、木材に金属の板などを締結するのに使われるネジです。木ネジのように抜いたり締めたりを繰り返すことはまったく想定してない、一回きり用のネジなの。
ピッチ (ネジの螺旋の間隔) も木ネジより細かく、つまり一度木ネジで空けられた木材の同じ穴にタッピングネジを締め込むと、螺旋のピッチが異なるため木の繊維が切り刻まれて、二度とネジが効かない “バカ穴” になっちゃうのよね。
そうなると、次の年にまた同じ穴に入れてもネジが効かないわけだから、毎年毎年…ネジを斜めに斜めに刺して、効きそうな角度を探しながらネジを締める…。
バカ穴に埋め木さえしていれば良かったのに…無知って怖いですよね。
埋め木もせずにグリグリグリグリ…ピッチの細かいタッピングネジであっちこっちと次々ほじくられてたら、博多駅前くらいの穴だって簡単に空いちゃいますよ。
部所有の木枠を著しく劣化させるのは『横ビス式の仮縁』だった…ってことです。
『ウチで使ってる仮縁は横ビス式じゃないから大丈夫』って思った先生、その木枠…今までに何回張り替えられてるか、把握なさってますか?

普段の “点検” と “管理” もメンテナンス。
いつ購入して、何回張ったか…。もちろん正確である必要はありませんが、だいたいは把握しててくださいよ。
まったく把握できていなかったら “管理能力ゼロ” ってこと。
そういう学校は、美術部所有の木枠を部員に貸し出してキャンバスを張らせるのは…もう終わりにすべきです。
生徒さんが精魂込めて描いた力作を、“木枠が部の所有” ってことだけで、剥がされて巻かれて持ち帰らされる。
親だって、『そんな状態で持って帰って来て、どうやって飾ればいいんだよ!』ってなります。

経済学的に見ても、正しくないんです。
『壊すために作る』っていう行為が、経済学的に見て生産性が有るとは言えないのと一緒。
( “壊すために作る” のは、造作物の強度や耐久性を分析したり統計を取るために行う実験的行為であり、生産性とは別な意味があるから製造業の現場に限って行われています)
この実験的行為は…費用がかかるだけで、そこから直接の利益は生まれません。つまり、“非生産的な行為” ってことです。

つまり、誰も喜ばない行為なんです。
この前の “経済学レクチャー” で話したラーメンのたとえバナシで言えば、ラーメン屋店主が1,000円の費用をかけてラーメンを作り、誰にも食べさせず下水に流してしまうってことと同じ。
『捨てるためにラーメンを作る』。これも非生産的な行為でしょ?
でも、効果ゼロではありません。
店主の経験値が1食分…上がってます。
でも、たったそれだけ。
他の人は誰も喜びません。
生徒さんが力作を描いても、剥がさなければ持って帰れない。
そんな無惨な状態の作品を、親御さんは喜びませんよ。
確かに生徒さんの経験値が上がったのかもしれませんが、剥がされた作品を親御さんは喜びません。

高美展で賞を獲っても全国大会に行っても、剥がされて巻かれて持って帰らなければならないなんて…。
生徒さんや親御さんの立場から見たら “屈辱” ですよ。
先生方、目を覚ましましょう。
『手張り』は、部がケチるためにやることじゃないんです!
ケチな部には手張りは向きません。
木枠を、耐用年数を超えて使ってしまったのであれば…その時点から “便益” はマイナスに転じているんです。
つまり部員さんたちはみんな、価値の無いモノを…労力をかけて作らされてることになります。
また、剥がされた作品を生徒さんの家庭で張り直したりするコスト (費用) を…全然計算に入れてないじゃないですか!
こんなの、経済学的に見たらインチキな統計ってことになります。
(安部政権下でさまざまな統計の数字がいじられ、インチキな経済政策が行われていたことはみなさんもご存知でしょう?)
部がケチって浮かせた金額以上の『損失』が、顧問の見えないところで発生してるんですよ。
3ダースが言う『結局トータルで見たら、機械製の張りキャンが一番安いです』ってコトバ、よく考えてみてください。
みなさんが気付けもしない…さまざまなコスト (費用) や、利便性の低下によるマイナスな経済性などをすべて勘案した上で『張りキャンが一番安い』って “経済学士” が言ってるんです。
生徒さんが精魂込めて描き上げた素晴らしい出来の作品を…木枠から剥がしてしまった時点で、経済学的に見たら明らかな損失になるんです。
こんなこと、ちょっと考えたらわかること。
ケチろうケチろうって思って、周りの多くの人達が損をしてるって、顧問だけが気づけてない。

手張りをするより、トータルで見たら張りキャンが一番安いんです。
でも…それでも3ダースは、張りたがってる生徒さんには張ってほしい!
正しい常識を身に付けた顧問の先生が…生徒さんに張らせたいって思うのなら、応援したい!
ですので、そういう気持ちの生徒さんや顧問の先生には…『生徒さん個人が木枠を所有し、その木枠に張らせる』ということをご提案いたします。
管理・点検・修繕すらもまったく出来てない部が…木枠を所有することは、もう終わりにしましょう。
たぶん次回に続きます。
【第37回終わり】