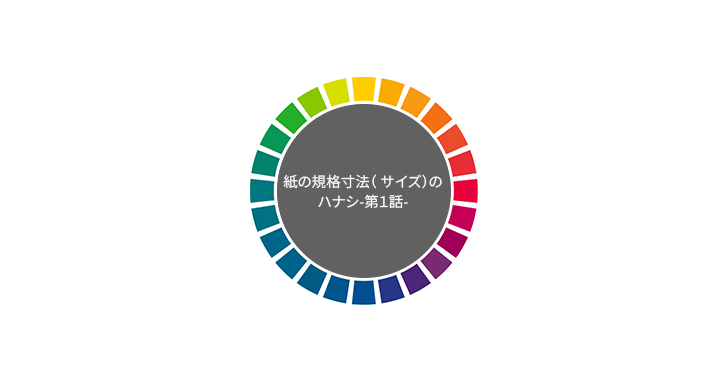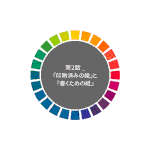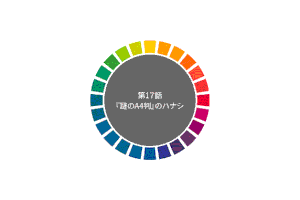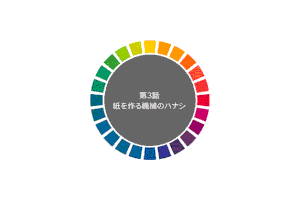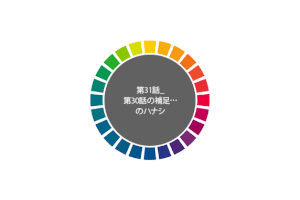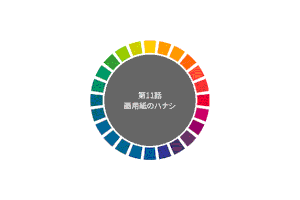【紙の規格寸法 (サイズ) のハナシ】
よくみなさん、A4 (えーよん) とかB4 (びーよん) とかって紙の大きさを呼んでますが、それらをJIS規格に従って正確に言うのなら『A列4番』とか『B列4番』と呼ばねばなりません。
でもご安心を。
普段からJISの正式名で紙のサイズを呼んでる人は全人口の0.005%居るか居ないか…です。
ですので、普通に『A4』とか『B4』って呼んじゃって大丈夫です。

A列は国際規格 (ISO=国際標準化機構による規格) で決められているもので、一方のB列は日本独自の規格 (JIS=日本工業規格…現在は改称されて日本産業規格) なのです。
(正確に言うと日本のB列とは微妙に違う『国際規格のB列』っていうのも存在するんですが、採用してる国も少ないし…日本国内では “国際B列” はまったく通用しませんから、国際B列は覚える必要はありません)
A列の発祥は戦前のドイツの工業規格。
それが戦後に世界標準となり、ISO規格に採用されました。
(ちろん日本のJIS規格にも、そのまま取り入れられています)
みなさんご存じの通り、紙のタテヨコ比率は『1対ルート2』。
すなわち『1:1.4142…』です。
この紙を…長辺が半分になるように切ると、切る前の紙とまったく同じ比率の紙が…半分の大きさで2枚作れます。

美術の世界にも深く関わっていたオストワルトさんは、“オストワルト式色立体” も考案してます。
(日本では “オストワルト式色立体” より、“修正マンセル色立体” や “日本色研PCCS色立体” の方がはるかに利用頻度が高いようですが…)
で、A列0番の紙の “面積” が『1平方メートル』となるように紙のタテヨコ比を割り振ったのが、現在の国際規格にも使われている『A列規格』です。
A1はA0の半分の大きさですから、0.5平方メートルの面積の紙ってことです。
A2はA1の半分ですから、0.25平方メートルの面積の紙ってことです。
番手 (数字) がひとつ増えると面積が半分になるんです。
逆に番手がひとつ減ると面積は倍…です。
次は、A列と日本独自のB列の関係を見ていきましょう。
同じ番手のAとBを比べると、Bの方が大きいですよね?
コピー用紙のA4とB4なら、B4の方が大きい。
比べてみればわかります。
でも計算すると、もっとよくわかります。
B4はA4の1.5倍の面積なのです!
そう。つまり…B列0番を1.5平方メートルの面積の紙になるようにタテヨコの比率を割り振って作ったのが、JISのB列規格です。
同じ番手ならB列はA列の1.5倍の面積。
その逆を見れば、同じ番手ならA列はB列の0.666…倍の面積。
番手のひとつ違うAとBとを比べる場合…、A3とB4なら当然A3の方が大きいんですが、面積比は1.333…倍。
ま、細かい数字なんかは覚える必要はありません。

『AだろうがBだろうが、同じ “列” の中なら、番手 (数字) がひとつ増えれば面積は半分になる』
『同じ番手 (数字) で比べればA列よりB列の方が面積比で1.5倍デカイ』
『A列はドイツ発祥の国際規格で、A列0番の面積が1平方メートルになるように割り振られた』
『B列は日本独自のローカルな規格で、B列0番の面積が1.5平方メートルになるように割り振られた』
なお、『A4判』とか『A4版』という紛らわしい漢字表記はご注文の際に使わないでいただきたいのです。 紙の断裁のご注文なら、『A4規格』か、単に『A4』と書いていただくのがベストです。 後々調べましたらご紹介したドイツの学者、オストワルトさん。 物理学者としてご紹介いたしましたが、実際には『化学者』でした オストワルトさん、ノーベル化学賞も受賞してる人です。 しかし、物理学的手法を用いて化学の研究をする “物理化学” という学問分野を確立した人でもあるそうで、当然物理分野にも詳しかったと思われます。 ネット上で “紙の規格” に関する記事を検索すると、ほとんどの記事でこの人の名前の表記が『オズワルド』になってるんですよ。 これ、オストワルト (Ostwald) の英語読みなのかな?…と思ったらオズワルドのスペルはOswaldで、つまり…別な名前になっちゃってるの。
記事を書いたヒトって、オストワルトさんの事…なにひとつわかってないんでしょうね。 “あの有名な” オストワルトさんのことを全然違うオズワルドって書かれちゃうのは、すごい違和感なんです、3ダースにとって…。 なぜなら、3ダースはオストワルト式色立体を知ってる世代ですからね。
今でこそオストワルト色彩理論は日本では完全に…完全に下火ですが、以前はオストワルトかマンセルかってくらい、オストワルトさんの存在は大きかったんです。
オズワルド表記で適当に記事を書いているヒトは、オストワルトさんの化学や美術の分野での活躍をまったく知らないみたいですね。 そういうヒトたちは、きっと複数のことを調べることができない “バカな子” なんでしょう。 『オズワルド表記』はバカな子の記事をあぶり出す…一つの指標になりそうですね。 あと、3ダースが四六判のウンチクばなしで紹介した『30 × 40インチのクアッドクラウン判 (クラウン判の4倍判) 』っていうイギリスの紙の規格寸法も、ネット上のほとんどすべての記事では間違ったことが書かれていました。
最初…数十件の記事を見比べていたら、『30 × 40インチの “クラウン判という大きな紙” があった』ってのと『20 × 30インチのクラウン判を “倍にしたもの” が30 × 40インチで…』と、四六判のもとになるはずのクラウン判のサイズにブレがあったんですよ。 しかも倍も違うって、どういうこと? 日本語のサイトでは『クラウン判は30 × 40インチ』ってのが圧倒的に多かったんですが、多いからといって信用はできません。 で、英文のサイトを見てみて愕然ですよ。 これ、全然ちっちゃいじゃん! 他の英文のサイトもけっこうな数見ましたが、クラウン判が20 × 30インチだとか30 × 40インチだなんてどっこにも書いてありません! (ちなみに20 × 30インチはダブルクラウン判、30 × 40インチはクアッドクラウン判、40 × 60インチはダブルクアッドクラウン判とのこと)
つまり、多くの “バカな子” が書いている『イギリスから輸入した30 × 40インチのクラウン判がもとになって四六判が生まれた』ってのは、日本で作られたデマだったんですよ。 正しくは3ダースが書いたように『イギリスから輸入していたクアッドクラウン判より…少し大きな紙を改めて輸入するようになり、それがもとになって四六判が生まれた』ってのが本当。
もう、ネットの世界はバカばっかり! なぜ裏取りしない?
ネット上に存在するほぼすべての記事の方が間違ってた…ってことですわ。
3ダースはパソコンも持ってないし携帯はいまだに二つ折りです。 他の記事はすべて出どころが同じ “ガセ記事” だったってことですよ。
論文に添付したイギリスからの輸入紙のデータも、著者の調査自体が甘く…手元の資料の誤りを見抜けないまま論文に添付しちゃったんでしょう。 ま、この論文著者も、裏取りができてなかったんですね。結果、ウソを撒き散らしちゃったわけですけど…。 あ、バカだから出来ないのか…。 あと、印刷業界の人は間違いなく『B全=B本判』っていう認識のハズだろうと思ってネット上の記事を見ていたら、印刷業界のヒトのくせに『B全=B1』なんて書いてるヤツもいるし…。
とにかく、ネット上のバカな子の記事には気をつけましょうね
鵜呑み厳禁よ。
【第1回終わり】

オストワルトさんの紹介訂正について

つまり化学が専門の人。鵜呑み厳禁
オズワルドっていったらケネディ大統領を暗殺した犯人じゃん!
(最近ではオズワルドといえば伊藤・畠中のお笑いコンビでしょうけど…)
普通に調べているのなら『オストワルト』さんを『オストヴァルト』か『オストワルド』に読み替えるのは有り得るけど、『オズワルド』に読み替えるのは無理って気づくはず。
っていうか、職業として販売してましたもん、色立体…。ソロバンの玉みたいな形の…。
ちなみに、色立体のメーカーさんに聞いたら…もう二十年くらい前にオストワルト式は廃盤になったそうで、今…特注で新規に作ると100万円越えるらしいです
Wikipediaすら見てないみたいだもん。
このテの記事には他にも致命的な間違いがいろいろ潜んでますので “オズワルド表記” の文章を見かけたら…内容を鵜呑みにするのはご注意ください。
“裏取り”してから掲載しましょう!
『ISO規格を採用する以前のイギリスに存在したクラウン判の寸法は、15 × 20インチ』
!!!
これじゃあB3程度の大きさですから!
日本語版のWikipediaにも間違って書かれています。
調べりゃわかるでしょ!
(実際は3件ほどクラウン4倍判と書いた正しい記事がありました。その記事を書いた人達は、もちろんバカな子ではありません)
でも、こんなアナログ人間でも簡単な “裏取り” くらいはできる。
なぜ、パソコンやスマホを持ってる世の中の大勢ヒトたちはネットに書き込む前に “裏取り” しないのかなぁ?
ま、その大もとの記事なのであろう昭和53年の “論文” までたどれましたけど…論文内に何個何個も誤字脱字のある著者でしたわ。それに致命的な数字の間違いも複数… 
じゃあ仕方ないか。