はじめに
キャンバスの手張りのハナシは次週かその次の週に再開します。
今回はキャンバスの「歴史」をザァ~っと辿ってみたいと思います。
油絵は最初からキャンバスに描かれていた?
現在、油絵には亜麻の枠張りキャンバスを使うのが定番ですが、油絵は最初っからキャンバスに描かれていたと思われますか?
いえ、実は**「油絵の技法の完成」と「枠張りキャンバスの普及」には…大きな大きなタイムラグ**があるのです。
缶詰と缶切りの例
ご存知ですか?
「缶詰の発明」と「缶切りの発明」も、数十年のタイムラグがあったんですよ。
缶切りが無い頃…缶詰を開けるのには、トンカチとノミ(あるいはバールのようなもの)でこじ開けるくらいしか…方法が無かったらしいです。
初期の油絵は何に描かれていたのか?
では…枠張りキャンバスが普及する前の油絵は、いったい何に描かれていたのでしょうか?
初期の油絵の基底材(支持体とも言う。絵を描く物。土台)は…**『板』**でした。
『木の板』!
しかも、枠張りキャンバスが一部で使われ始めてからも、油絵の基底材は圧倒的に板が選ばれていました。
だいぶ長い期間、板こそが最高の基底材って信じられていたのでしょう。
キャンバスが完全に板に取って代われるまで、100~200年かかったと言われています。
すごいタイムラグですねぇ😲
モナリザも板に描かれていた
実は、あの有名な『モナリザ』も基底材はポプラの板なんですよ。
まぁ、これは有名なハナシ。みなさんご存知ですよね?
モナリザは、それほどデカイ絵じゃありません。
約77×53㎝。
つまり、20号程度(P20を約4㎝長くしたくらい)です。
板をつなぎ合わせて大きな絵を描く
当時、ベニヤ合板のように広い面積の板なんかはもちろん存在しません。
ある程度の大きさの絵を描く場合、何枚かの細い板をニカワ(接着剤)かカスガイ(釘の一種)でくっつけて、大きい板を作っていました。
もちろんモナリザも、複数の板をくっつけたものに描かれています。
なぜ「細い板」を使うのかというと、板の幅が広ければ…それだけ**『反るリスク』**が大きくなるからです。
巨大な作品は描けなかった
つまり板を使って描いている限り、巨大な作品は描けません。
キャンバスが普及するより前、巨大な絵は建物の内壁に描くしか他に方法がありませんでした。
レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』は建物の壁にテンペラの技法で描かれましたが、その後の『アンギアーリの戦い』は壁に油絵で描かれた…と言われています。
(未完成にて逸失しているので本当に油絵で描かれたのかは不明。あるいは別な壁の奥に未完の状態で隠されている…?)
もちろん、建物の壁に描かれた絵は移動することなんか出来ません。
『絵といえば板か壁』の時代、移動可能な巨大な絵の制作は不可能でした。
ベネチアでキャンバスが普及した理由
絵画用の枠張りキャンバスが最も早く普及したのは**『水の都』ベネチア。**
ベネチアは地中海の海運と造船の中心地でした。
理由1:木材不足
船を作るのには大量の木材が必要です。貿易が盛んになると、当然船も大量に建造されます。必然的に、絵を描くための板は入手しづらくなります。
理由2:湿気の多い土地柄
また、ベネチアは湿気の多い土地柄、板の絵はすぐにダメになってしまいます。
湿気で板は反ったり伸縮したりしますので、せっかく板をくっつけ合わせて広い面積の作品を作っても…接合部が割れてしまうこともしばしば。
場合によると腐ってしまったり…。
理由3:運搬の利便性
また、陸上で絵画を運搬するのにも、運河や水路に掛かった橋を渡ったりするため…なるべく軽い方が都合が良いわけです。
(ベネチアの橋は、ゴンドラや船が通るため…橋の中央部が高くなっていて、ほぼすべての橋には階段がもうけられています)
板の絵は重かった
当時の板に描かれた油絵は、板に直接絵具を乗せていたわけではありません。板を白亜や石膏で塗り固め、いわば壁のような下地を作った上に絵具を乗せていたのです。
つまり、板の絵は…基底材の状態でもけっこう重かったのです。
キャンバスの普及
そんなわけで、『絵といえば板か壁』と決まっていた時代のベネチアに、板に代わる基底材として…軽くて大きな面積も作れる枠張りキャンバスが広まりはじめました。
布は、前にも述べましたが…帆布(はんぷ)を流用しました。
帆船のための帆布は大量に織られていましたし、そのための亜麻の栽培も盛んでしたから…。
キャンバスは「板の代用品」だった
基底材として枠張りキャンバスが普及し始めた頃…枠張りキャンバスの立場は、あくまでも板の**『代用品』。『板を模した物』…。**
ですから、今でもパンッパンに強くキャンバスを張るのはそのためです。
カーテンのようにゆるゆるな張り具合のキャンバスでは、基底材として役に立ちません。
現代人は「布」と思っている
しかし現在、一般のお客様や学生さんなど…多くの人は枠張りキャンバスを**『布』**と思って見てしまうようですね。
『油絵を描く「白い布」くださ~い』なんて言ってきますから…。
しかし我々は、枠に張られたキャンバスを「布」とは思っていないので、そう言われるととても違和感があります。
もちろん、枠に張る前のカットキャンバスやロールキャンバスは当然『布』だと思って見ていますが、枠に張り上げたキャンバスは完全に『板!』というイメージで我々は考えておりますので…。
キャンバスのメリット
さて…そんな枠張りキャンバスですが、板に比べてはるかに軽いし、板と違って面積の大きいものも容易に作れます。
メリット1:割れない・反らない
くっつき合わせた板のように割れたりしないし、反ることも少い。多少の湿気にはびくともしません。
確かに、木枠の木材が反ったりねじれたりして画面が歪むことは有るかもしれません。でもそんな時には新しい木枠に付け替えれば歪みは解消します。
メリット2:巻いて運搬できる
枠から剥がして巻き、移動先で再び枠に張る…という**「裏技」**も可能。
現地で新しい木枠を製作すれば、重い木枠を運ばずに済みます。
宣教師はそのようにして宗教画を新大陸やアジアなどに運びました。
「夢の基底材」へ
このように…板を超越した、枠張りキャンバスにしか無いメリットに多くの人々が気付き、『板の代用品』でしかなかったキャンバスは無限の可能性を秘めた『夢の基底材』へと育って行ったのです。
【第21回終わり】

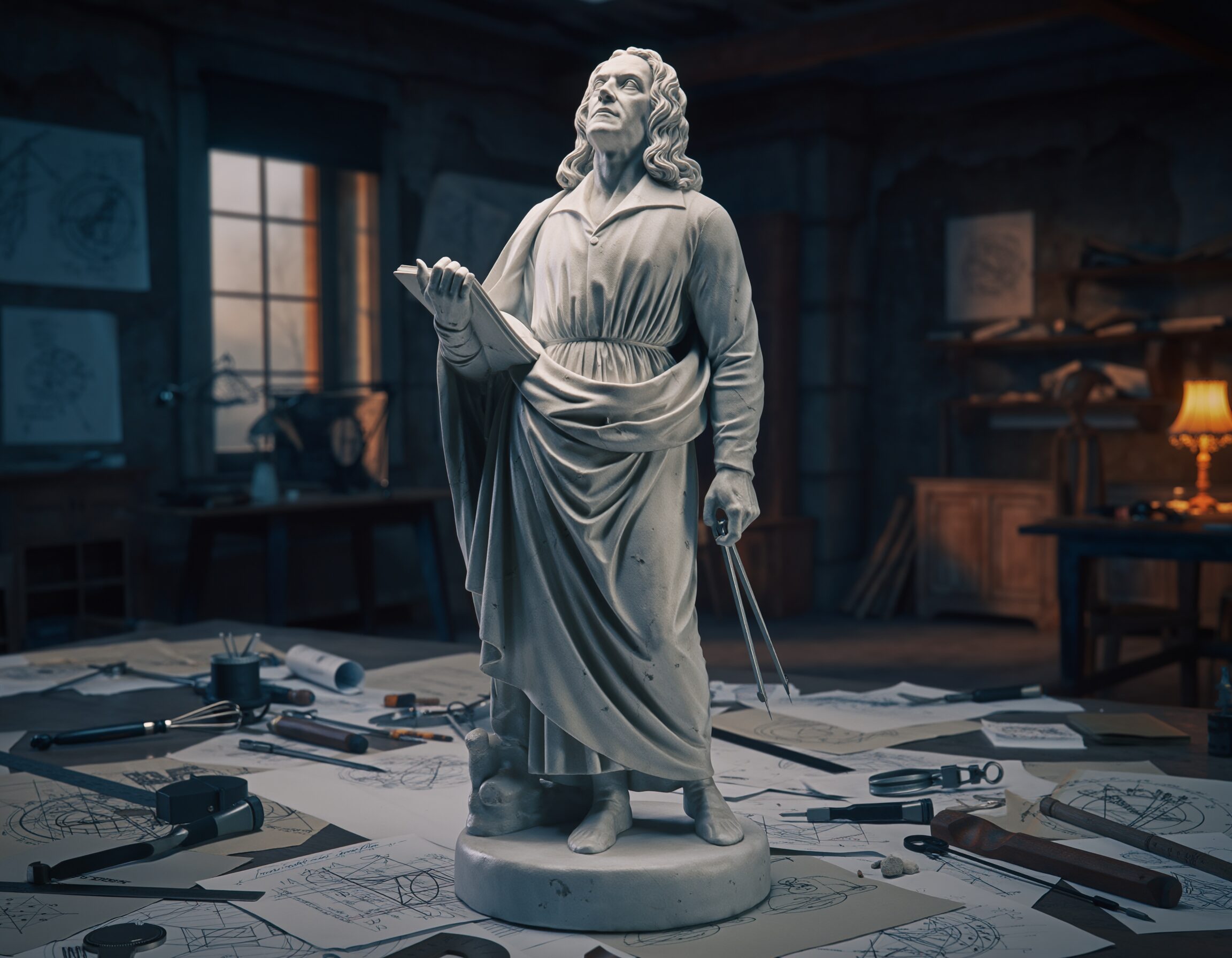



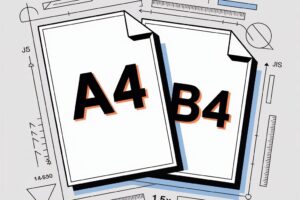







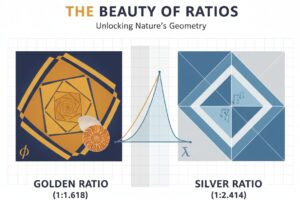



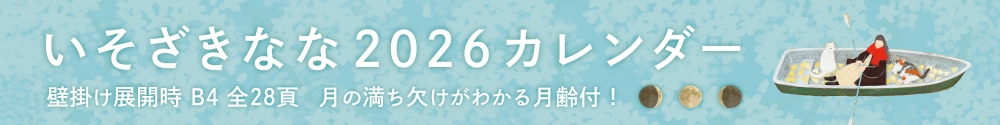





コメントを残す