はじめに:あれは芸じゃない、マジギレだった
前回のメルマガには『3ダースサンのキレ芸炸裂😆』などの感想が届きましたが、アレは “芸” ではありませんし “ネタ” でもありません。
本当に紙問屋さんに対してキレたんですよ。マジで。
納得してない「A4判」問題
世の中的に “A4判” と言えば『JIS規格のA列4番』のことです。 原紙である “A本判の8切” は…どう逆立ちしても『A本判の8切』でしかなく、”A4判” などと名乗ってはいけないと3ダースは思うのです。 そんな…自社内でしか通用しない『A4判』を、こちらに確認もしないで適用されたことにキレたのです。
その後…紙問屋さんとは和解はしましたが、”JISのA4よりひとまわり大きいA4判” の存在には納得してません。木枠のP4の寸法も間違ったままだし…。 こちらとしては、資料ページの記載間違いを指摘し…何度も訂正依頼をしてるのに無視し続けられてたんですから、そりゃキレますよ。
水素結合の詳しい説明リクエスト
あと、『紙のハナシを終わりにする前に、セルロースの分子がくっつき合う水素結合の詳しい説明をしてほしい。放ったらかしにして逃げないで』との声も届きましたが、この先生は本当に説明聞きたいのかしら?
それとも…理系から遥かに遠い位置にいる3ダースを…ただ苦しめたくておっしゃってるんじゃありませんか?
でもまあ、乗り掛かった船…。 もう少し紙のおハナシをさせていただきたいと思います。
パルプとセルロース
パルプとは…セルロースからなる繊維の集合体。 セルロースとは、植物の細胞壁の主成分。
こう…コトバで言ってしまえば簡単ですが、なかなかイメージ出来ませんよね。
カット綿で理解する
ちょっと乱暴な例えですが…カット綿 (脱脂綿・コットン) をほぐすと、もっのすごく細い…モヤモヤした糸状の繊維が見られますよね?
あれがセルロース繊維って思っていただいて良いと思います。
『ちょっとちょっと3ダースサン、あれは綿花から採れる繊維でしょ? 普通の紙に使うのは木材パルプが圧倒的に多いって自分で言ってたじゃないですか! 木材のどこにコットンの繊維みたいなモヤモヤしたのが有るんですか!』 なんて叱られちゃいそうですが、木材からもああいうモヤモヤした繊維が取り出せるんですよ。
綿毛は細胞の死骸
じゃあ…まず、コットンのモヤモヤした繊維がどんなものなのか調べてみましょう。 『種子から生える綿毛で、もともとは種子の外皮細胞が変化したもの。細胞壁で出来た細長い管状で、中は液体で満たされている。種子の成熟と共に綿毛の細胞は死滅し、水分は枯れ、中空の繊維になる』とのこと。
あら、あの綿毛って “細胞の死骸” だったんですね。
木のほとんどは細胞の死骸
あ、そうだ。 死骸って言えば…みなさんご存じでした?
木ってほとんどの細胞が死んでるんですよ。
長年の疑問が解消
3ダース、昔から考えてたことあるんですよ。『森林の木、細胞すべてが生きてるのかなぁ?』って…。
だって、木って相当な体積じゃないですか。 すべての細胞が呼吸して代謝してるのなら、酸素もエネルギーも全然足りないんじゃないか…って。
今回のメルマガ執筆を機に樹木のあれこれも調べることが出来、長年の疑問が解消しました。
結論を言うと、『木のほとんどの部分は…細胞の死骸で出来ている』ということなんですよ。 (人間も…爪とか、あと皮膚の表面なんかは死んだ細胞ですよね😅 )
誤解されている「木は生きている」
おそらく、ほとんどのヒトが、『木は生きている』というコトバを “木はすべての細胞が生きている” と理解しちゃってるはず。 でも、実際はそうじゃないんです。
生きてるのは幹や枝や根の先端 (成長点) 、そして光合成の役目を担う葉っぱの細胞。それらはもちろん生きています。 しかし、幹の内側…すなわちすでに年輪が出来ているような部分には、生きてる細胞なんかいないんですよ。
幹や枝や根の “胴体部分” は…外皮の内側の、ほんの少しの厚みの部分にしか、生きた細胞は存在しません。そのかわり、その少しの厚みの部分に “形成層” という部分があり、活発に細胞分裂をしています。要は、形成層が徐々に外側に広がっていって、内側に細胞の死骸が残されて年輪を形成するってイメージですね。
なぜ木は細胞を死なせるのか
なぜ木は、自分の体の細胞の大部分を死なせてしまうのでしょうか? 生かしておかないのでしょうか?
それは、『木』が生き抜くための選択だったのです。 『木』が生き続けるために、大部分の細胞に犠牲になってもらっているのです。
細胞壁の役割
幹の内部の細胞は死ぬことにより、みずからの細胞壁を木の骨格とします。 また、みずからの細胞壁を水の通り道として『木』のために提供します。
世界で最も高い木は115mを超えるそうです。 その巨体を支え、先端にまで水を吸い上げるには硬い細胞壁の骨格と…頑丈な水の通り道が必要なのですが、生きた細胞にはその役目は担えないのです。
草と木の違い:リグニン
『細胞壁』すなわちセルロース繊維からなる構造体は、植物や菌類や細菌類だけがもつ骨格です。
埼玉県民が主食としている “そこらへんの草” なら、細胞壁のセルロース骨格で十分なのですが、『木』にはそれだけでは強度不足なのです。
草と木との違いは『リグニン』という物質の有無!
“木” が “木” 足り得るのは、リグニンあってこそ!
リグニンとは
リグニンとは…細胞と細胞をくっつける接着剤のようなもので、木が自分自身で作り出した物質です。 細胞壁の内側にも徐々に沈着して行って細胞壁を厚くし、細胞壁の強度を高めます。 このリグニンは、細胞が死んでから顕著に蓄積するのです。
リグニンにより厚くなった細胞壁が、木の内部の圧力にも潰されないような水の通り道の管を形作り、また100m近い巨木になっても倒れない頑丈な骨格を作るのです。 木の幹の内側は、リグニンで固められた…セルロースによる管状の組織がぎっしり詰まっているんです。
まぁ、管って言っても…ものすごく細いですよ。顕微鏡レベルです。
綿花と木の繊維は同じ
ほら、コットンの綿毛と同じような状態でしょう?
『細胞壁で出来た細長い管状』『細胞は死滅していて中空の繊維』…。 ね? 綿花の繊維と木の繊維、ほとんど同じじゃないですか?
木の幹の内部の繊維を、針葉樹の場合は『仮道管 (かどうかん) 』と呼び、広葉樹の場合は『木繊維 (もくせんい) 』と呼びます。どちらも極細の管状の構造です。
リグニンとパルプ化
ところで…先程から連呼してますが、『リグニン』って覚えてらっしゃいますか?
紙を変色・劣化させる厄介者でしたよね。 でも、木にとっては必要不可欠な物質だったんですね。
パルプ化とは
このリグニンをセルロース繊維から分解・除去し、セルロース繊維だけを取り出すことを『パルプ化』といいます。
現在主流になっている『クラフトパルプ製法』なら、リグニンを完全に除去できます。
しかし、大事なセルロースまで分解し…逸失してしまうので、原料に対してパルプを得られる効率は悪く、クラフトパルプは高価になります。よって、クラフトパルプは上質な紙に使われます。
更紙や新聞用紙には、リグニンが混在してしまう機械的製法のパルプが使われます。
セルロースの正体:ブドウ糖
さて、リグニンを除去され、パルプ化されたセルロース繊維ですが、このセルロース、どんな物質で作られているかご存じですか?
ご存じの方も多いはず。
そう、**『ブドウ糖』**です。
甘くないブドウ糖
『え、じゃあセルロースって甘いの?』って思われました?
いいえ、ちっとも甘くありません。 っていうか、栄養にすらなりません。 なぜなら消化吸収されませんから…。 つまり、そのまま出ちゃいますから…。 みなさんが言う “食物繊維” って、だいたいセルロースのことですから…。
はい。 ブドウ糖で構成された高分子化合物で、炭水化物の一種ではありますが、人間はセルロース分解酵素を持たないので消化も吸収もできないのです。 ヤギなどは、消化管の中にセルロース分解酵素を持つ微生物が生息しているので、その酵素を利用して植物のセルロースを分解しています。 (第11回で『ヤギなどはセルロース分解酵素を持つ』…と書きましたが、厳密に言えばヤギ自身は分解酵素を持っていません。失礼しました)
デンプンとの違い
ブドウ糖からなる高分子化合物、他にもありますよね?
そう。 デンプンです。
デンプンはブドウ糖が螺旋状につながり、セルロースは直線状につながったもの。結合の形状が違うので、分解出来る酵素も異なるのです。
デンプンもセルロースも植物の内部で合成されます。
叩解:繊維をほぐす作業
さて、パルプの状態になったセルロース繊維ですが、まだこのままでは紙にはなれません。 繊維を叩解 (こうかい = たたいてほぐす) する作業が必要なのです。
もっとも、叩解って呼んでいたのは和紙を作る工程で、実際にパルプを叩いてほぐしていたから…。
リファイナー
現代の製紙工場では、『リファイナー』という機械を使います。無数の刃が付いたディスクを2枚擦り合わせ、その間に水とパルプを通すんです。そして繊維を切ったり裂いたり…すりつぶしたりするんです。 こうすることにより、筒状の細長い繊維だったものが適度にちぎれて毛羽立ち、ほぐれていきます。するとセルロース分子の “手” になる部分が次々に出現します。
セルロースの「手」
“手” って、化学に詳しい方ならもうおわかりですよね? 『OH基』ってやつです。 あ、そんなの覚える必要ないですよ。このメルマガ内では『手』で通しますから。
この “手” 、本来はひとつの鎖状の分子構造の中で…しかるべき相手とつながり合っていたわけですが、叩解作業によって…要はフリーになるわけです。
セルロース分子は親水性がある…って以前言いましたよね。
この『手』は、水分子とやたらとくっつきたがるんです。だからすぐに水分子を捕まえます。
この捕まえるってのが、セルロース分子と水分子の水素結合です。
抄紙:ひたすら水を抜く作業
このリファイナー叩解の済んだパルプは填料とにじみ止めの薬品などと混ぜられ、抄紙作業に移ります。 原料 (パルプや填料などの固形物) 1に対し、99倍の水で薄められた “懸濁液” を抄紙機に流していきます。
ワイヤーパート
まず最初の工程が『ワイヤーパート』。ワイヤーと言ってますが、網です。昔は金属だったようですが今は樹脂製の網…。
幅広で長い網がベルトコンベアみたいにエンドレスで回っているんですが、そこに懸濁液が流されます。 一定の厚さで網に乗るように調整されていて、けっこう速いスピードで網は動いていきます。 ここで、水分だけは網の目から下に落ちるのです。
ワイヤーパートで、原料の99倍あった水のほとんどが脱水され、原料1に対して4程度の水の量になります。
プレスパート
次がプレスパート。 プレスロールとフェルトで挟まれた紙は更に脱水され、原料1に対して3分の2の水の量になりました。
乾燥ドラム
そこから乾燥ドラムという、熱を帯びた筒をいくつもいくつも潜り抜け、原料に対して数%の水の量になります。
このように、抄紙のプロセスは、懸濁液だった原料からひたすら水を抜いていく行為の連続なのです。
水素結合の一部始終
懸濁液の状態だった原料内では、セルロース分子の “手” は水分子を掴み、その水分子はセルロース分子に捕まえられたことにより隣の水分子を掴み、またその水分子は隣の水を掴み…と、水素結合が連鎖して起こり、ついにはその一連の水分子は別なセルロースの “手” とつながります。
セルロースの “手” と “手” が、水分子を懸け橋のようにしてつながったわけです。
やがて水は脱水され、乾燥され、減っていきます。 “手” と “手” の間の懸け橋の水分子も、次々に居なくなります。
そしてついにセルロース分子の “手” と、別のセルロース分子の “手” が、水素結合によって結ばれる…!
これがセルロース分子の水素結合の一部始終です。
おわりに:文系男子の精一杯
ふぅ。 『なげ~よ!』との罵声も聞こえて来そうですが、これが文系男子による…精一杯の “抄紙と水素結合の説明” です。
ホント、精一杯っす。 自分を誉めます、勝手に…。
【第18回終わり】












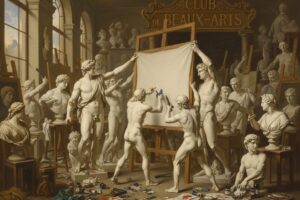
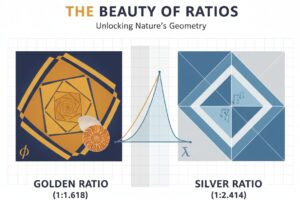



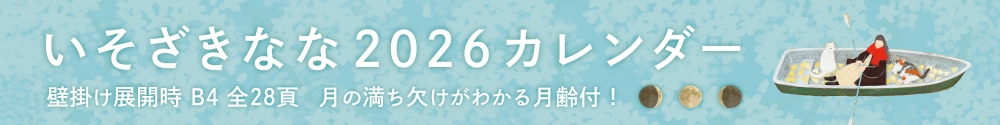





コメントを残す