画材を愛する皆様、こんにちは。今回は、小売店様からのお問い合わせも多い「引き通し筆」について、その歴史から構造、使い方まで解説致します。
引き通し筆って何?〜まずは基本から
**引き通し筆(ひきとおしふで)**とは、穂先の長さを自由に調整できる特殊な構造を持つ筆です。
別名として「サス」「サズ」とも呼ばれ、主に**蒔絵(まきえ)や金継ぎ(きんつぎ)**などの繊細な作業、そして日本画の細密描写に使われてきました。
「引き通し」という名前の由来
「引き通し」という名前は、その構造に由来しています。
筆の内部で糸が軸を通して(引き通して)穂先を支えている構造から、この名前がつけられました。穂先を引っ張ることで長さを調整できる、まさに「引いて通す」筆なのです。
なぜ穂先が取れるの?〜これは故障ではありません!
よくある誤解
引き通し筆を初めて手にした方から、最もよく寄せられる質問があります。
「穂先が取れてしまった!不良品ですか?」
答えは「いいえ、正常です」
穂先が取れるのは、引き通し筆の正しい仕様であり、故障や不良品ではありません。
穂先が取れる構造の理由
引き通し筆がなぜこのような構造になっているのか、その理由を見ていきましょう。
理由1:作業に応じた長さ調整機能
蒔絵や金継ぎ、日本画の細密描写では、作業内容によって最適な穂先の長さが異なります。
-
長い線を一息で引く場合 → 穂先を長く出す
- 墨や絵具、漆の含みが良くなる
- 手を止めずに長い線が引ける
-
細かい点描や装飾の場合 → 穂先を短くする
- 筆先のコントロールがしやすくなる
- 繊細な表現が可能になる
つまり、一本の筆で複数の用途に対応できるというのが、引き通し筆最大の特徴なのです。
理由2:日本の筆づくりの伝統技術
引き通し構造は、実は日本の筆づくりの長い歴史の中で生まれた、伝統的な技術なのです。
日本の筆の歴史〜引き通し筆のルーツを辿る
奈良時代:日本最古の筆「紙巻筆」
日本に残る最も古い筆は、**奈良・正倉院に所蔵されている紙巻筆(天平筆)**です。これは今から約1,300年前、奈良時代(8世紀)に作られました。
紙巻筆の構造:
- 中心に最も長い獣毛(芯毛)を立てる
- その周りに和紙を巻く
- さらに毛を巻く
- また和紙を巻く
- これを何層にも繰り返す
この構造は「雀頭筆(じゃくとうふで)」とも呼ばれ、穂先の形が雀の頭のように見えることから名付けられました。
紙巻筆は「有芯筆(ゆうしんひつ)」とも呼ばれ、芯となる構造を持つのが特徴です。
[出典:奈良国立博物館、筆の里工房、清晨堂ブログ]
江戸時代:「水筆」の誕生
江戸時代の元禄期(1688-1704年頃)、大きな変革が起こります。
学者・書家の**細井広沢(ほそい こうたく、1658-1736)**が、中国の筆製法を研究し、画期的な「水筆(すいひつ)」を考案しました。
水筆の特徴:
- 穂首全体が練り混ぜされている
- 紙を使わない「無芯筆(むしんひつ)」構造
- 穂首全体に調子(弾力)がある
- 墨含みが良く、使いやすい
- 短期間で製造できる
この革新により、筆は大量生産が可能になり、現在使われている筆のほとんどは、この水筆の系譜に連なります。
[出典:筆の里工房、攀桂堂 雲平筆]
引き通し筆:伝統と革新の融合
引き通し筆は、紙巻筆の調整可能な構造と水筆の使いやすさを融合させた、まさに伝統と革新の産物なのです。
引き通し筆の構造〜どうやって作られているの?
基本構造
引き通し筆は、大きく4つのパーツで構成されています:
- 穂先(毛の部分) – ネコの玉毛、イタチ、テンなど
- 糸巻き部分 – 穂先の根元を固定する糸
- 軸(竹や木製) – 筆本体
- 調整機構 – 糸が軸内部を通り、引っ張ることで長さ調整が可能
穂先が「取れる」仕組み
重要ポイント: 引き通し筆の穂先は、一般的な固定筆のように軸に完全に固定されていません。
穂先は糸で束ねられ、その糸が軸の内部を通って支えられているだけです。だから、引っ張ると取れるのです。
これは不良品ではなく、設計通りの正常な構造です。
引き通し筆の種類と用途
蒔絵筆として
引き通し筆の代表的な用途が蒔絵です。
蒔絵とは、漆器に金粉や銀粉で装飾を施す、日本の伝統工芸技法。極めて繊細な線描きが必要で、引き通し筆が不可欠です。
原材料: 白ネコの背筋の毛(玉毛)
- 白毛はメラニン色素がないため硬くコシがある
- 極細の線が引ける
- 冬毛が最良とされる
用途:
- 金泥、銀泥を置くように描く
- 漆で細い線を引く
- 極めて繊細な装飾
金継ぎ用筆として
近年、国内外で人気が高まっている金継ぎにも、引き通し筆が使われます。
金継ぎとは、割れた陶磁器を漆で接着し、金粉で装飾して修復する日本の伝統技法。海外では「Kintsugi」として注目を集めています。
最適な穂丈: 12〜16mm(金継ぎ作業の場合)
日本画用の面相筆として
日本画の細密描写にも、引き通し式の面相筆が使われることがあります。
用途:
- 極細の線描き
- 細かい模様の描き込み
- 繊細な表現が必要な部分
デザイン・レタリング用として
ゴシック文字や明朝体文字を描くための、デザイン用引き通し筆も存在します。
原材料: 日本産イタチ毛 用途: 文字描き、レタリング、デザイン作業
主要メーカーの引き通し筆
名村大成堂(東京)
創業: 1940年(昭和15年) 歴史: 80年以上の筆づくりの伝統
代表製品「精選 茶軸蒔絵筆」:
- 原材料:白ネコの背筋の毛
- サイズ:小・中・大
- 用途:蒔絵、金継ぎ、日本画
その他、「SN 丸ゴシック(イタチ毛)」「特選貂毫面相(テン毛)」なども製造。
[出典:名村大成堂公式サイト]
村田九郎兵衛(京都)
京都の蒔絵筆専門工房。上級者・プロ向けの高級蒔絵筆を製造。現在は品薄状態が続く。
久野(名古屋)
名古屋の蒔絵筆製造工房。比較的安定して製品を供給している。
熊野筆(広島県熊野町)
書道筆や化粧筆で有名な熊野町でも、一部の工房で蒔絵筆を製造。
特徴: 一度きりの長さ調整を前提に作られている(キツく作られている)
引き通し筆の正しい使い方
初回の長さ調整方法
引き通し筆を初めて使う際、最も重要な作業が長さ調整です。
手順:
-
軸を優しく持つ
- 竹製の軸は割れやすいので慎重に
- 力を入れすぎないこと
-
穂先の根元の糸をしっかり握る
- 毛ではなく、糸の部分を持つ
-
ゆっくりと下に引く
- 急に引っ張らない
- 少しずつ様子を見ながら
-
希望の長さで止める
- 用途に応じた長さに調整
- 金継ぎの場合:12〜16mm程度が使いやすい
重要な注意点:
⚠️ 完全に引き抜いてしまうと、元に戻せない場合があります
⚠️ 軸の耐久性を考えると、長さ調節は使用前の1回のみが基本
⚠️ 何度も調整すると、軸が破損する可能性があります
日常のお手入れ
引き通し筆を長持ちさせる秘訣:
-
水毛(毛先)を触らない
- 動物の毛は先端が極細で繊細
- 乱暴に扱うと傷む
-
使用後は油で保護
- サラダ油やナタネ油を含ませる
- 拭き取らず、そのまま保管
-
定期的な油の交換
- 長期間使わない場合(半年以上)
- 油が固まらないよう洗い直す
-
穂先を短く収納
- 保管時に毛先が曲がらない
- 専用のキャップや筒に入れる
固定筆との違い〜どちらを選ぶべき?
固定筆(現代の一般的な筆)
構造:
- 穂首の根元が練り混ぜされて固定
- 軸に差し込まれて固定
- 穂先の長さは変更不可
メリット:
- 安定した書き心地
- メンテナンスが簡単
- 一般的な書道や日本画に最適
- 価格が比較的手頃
デメリット:
- 穂先の長さ変更不可
- 用途ごとに異なる筆が必要
引き通し筆
構造:
- 穂先の長さを調整可能
- 4つのパーツに分解可能
- 糸で穂先を支える構造
メリット:
- 作業に応じた微調整が可能
- 極細の線描きに優れる
- 一本で複数の用途に対応
デメリット:
- 調整に技術が必要
- 軸が破損しやすい
- 価格が高め
- 入手困難な場合がある
どちらを選ぶべき?
引き通し筆が適している方:
- 蒔絵や金継ぎを学んでいる
- 極細の線描きが必要な日本画家
- 伝統技法を追求する工芸家
- 一本の筆を使いこなしたい上級者
固定筆が適している方:
- 一般的な日本画制作
- 書道
- 初心者から中級者
- 安定した使い心地を求める方
引き通し筆の現在と未来
製造の現状
残念ながら、引き通し筆の製造は年々困難になっています。
課題:
- 原材料の入手困難 – 特にネコの玉毛が年々入手しづらい
- 熟練職人の減少 – 手作業のため量産できず、後継者不足
- 製造コスト上昇 – 希少な材料と高度な技術が必要
新たな需要の芽生え
一方で、明るい兆しも見えています。
金継ぎブームの到来:
- 国内での認知度約70%(2024年調査)
- 海外で「Kintsugi」として人気急上昇
- SDGs意識で「修理して使う」文化が再評価
蒔絵・漆器の海外人気:
- 繊細な技術が海外で高評価
- 「MAKI-E」として国際的認知
- 伝統工芸品の輸出増加
本物志向の高まり:
- デジタル時代だからこその手仕事への価値意識
- 一生使える本物の道具を求める人々の増加
まとめ〜引き通し筆という宝物
引き通し筆は、日本の筆づくり1,300年の歴史が生んだ、繊細で美しい道具です。
覚えておきたい7つのポイント:
- 穂先が取れるのは正常 – 不良品ではなく、設計通りの構造
- 長さ調整が最大の特徴 – 作業に応じて最適な長さに設定できる
- 伝統技術の結晶 – 奈良時代から続く技術の進化形
- 蒔絵・金継ぎに不可欠 – 極細の線描きに最適
- 一度きりの調整が基本 – 何度も調整すると破損の恐れ
- 希少で高価 – 熟練職人の手作業による貴重な道具
- 一生使える本物 – 正しく使えば長く愛用できる
引き通し筆を手にすることは、日本の伝統工芸の世界への扉を開くことです。
その繊細な構造と、職人の技術の結晶である一本の筆を、どうか大切に、そして楽しんで使っていただければ幸いです。
参考文献:
- 奈良国立博物館「筆(正倉院宝物模造)」
- 筆の里工房「書筆-概説」「桃山・江戸時代」
- 清晨堂「東京藝術大学日本画科 筆講義 筆の歴史」
- 博多漆芸研究所「うるし徒然―蒔絵筆のはなし―」
- 攀桂堂 雲平筆「筆の起源と歴史」
- 名村大成堂公式サイト
- 金継ぎ認知度調査2024
- PR TIMES「金継ぎキットの海外売上が前年の26倍に」(2022年1月28日)
画材を愛する皆様へ
この記事が、引き通し筆という素晴らしい道具を知り、理解するきっかけになれば幸いです。
小売店の皆様におかれましては、お客様に「穂先が取れるのは仕様であり、不良品ではない」ことを、ぜひ丁寧にご説明ください。
一本一本が職人の手で丁寧に作られた引き通し筆。その価値を正しく理解し、次世代へと伝えていくことが、私たち画材を愛する者の使命だと信じています。













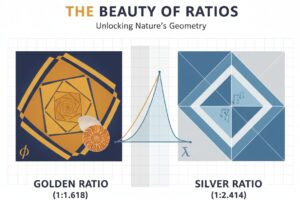


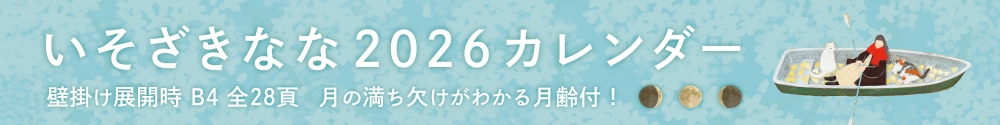





コメントを残す