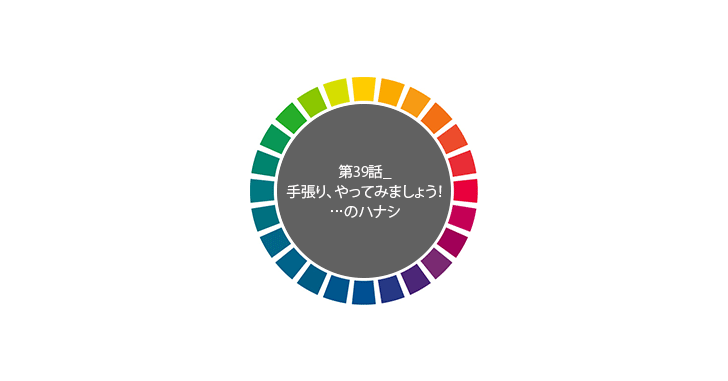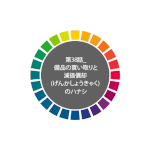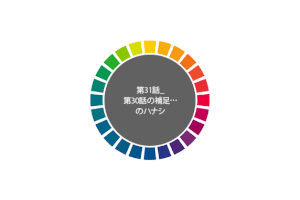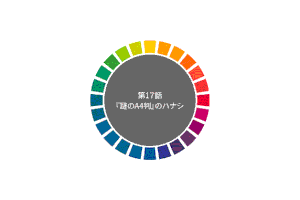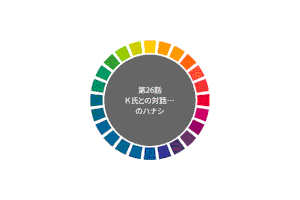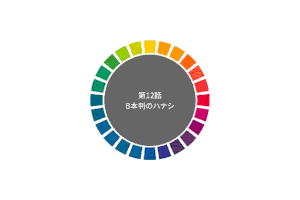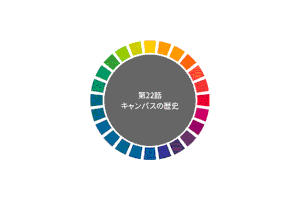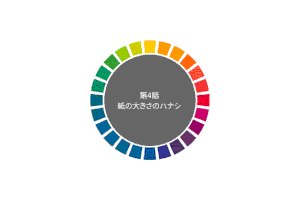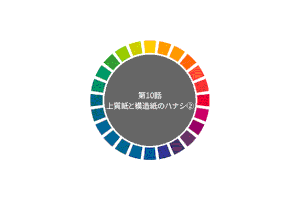手張り、やってみましょう!…のハナシ
『結局トータルで見たら、機械製の張りキャンが一番安いです!』とは言うものの、美術部員たるもの…キャンバスの手張りは経験しておきたい…。
また、顧問の先生も、手張りの指導をしておきたい…。

ただし、何度も申し上げていますように…機械製の張りキャンから布を剥がした残骸の木枠は、もはや使えませんよ!
また、張りキャンから抜いた丸い頭の釘も、手張りに使うのにはとても使いづらいと思います。
木枠のオモテ裏は間違わないように!
木枠は、“ナナメになってる方” が『オモテ』で、 “号数が書いてある方” が『裏』です。
この “ナナメ” って、二つの意味がありますよ。
カドの合わせ目が45°のナナメになって見えるという意味と、木枠のオモテ面に…画面中央に向かって少し下がるような “傾斜” がついていることです。
この傾斜こそがキャンバス用木枠の『命』なんです!
ヘリの部分が一番厚みがありますが、そのヘリ (側面とオモテの傾斜面の接するライン) をエッジと呼びます。
木枠を使い回すと釘穴や横ビス式の仮縁のネジ穴が空くだけでなく、このエッジがすり減って…凹んでしまうのでキレイに張れなくなります。
たとえ硬い『ベイスギ (ウェスタンレッドシダー) 材』の木枠であれ、何度も何度も何度も何度も何度もの張り替えには使えないのです。

そして、キャンバスを張る時は必ず一人で張らせましょう。
自分のキャンバスの張り具合は自分自身が責任を持つんです。
もし、張りが弱かったのなら…辺の中央付近の釘を何本か抜いて布を引っ張り直しましょう。
布を強めに引っ張れば、布に空いていた釘穴と木枠に空いていた釘穴の位置が若干ズレることでしょう。つまり、それだけ布が伸びてるってことです。
布が伸びたことを確認してから釘を打ちましょう。この際には、つい先程抜いた釘をそのまま使っても良いでしょう。
画面にシワやタルミがなくなるまで引っ張り直しを繰り返せば、完璧な張り具合になるはずです。
指でキャンバスを弾いた時に、鈍い “ボヨンボヨォン” という音ではなく、高めな “パンパンッ” という音がするくらいの張り具合を目指しましょう。
木枠に関して少しご説明いたしますが、実は…機械製の張りキャンに使われてる木枠って、手張り用に売られている木枠よりも厚み (釘が打たれる側面の幅) が薄く作られていることが多いんですよ。
ですから…機械製の張りキャンから剥がした木枠を手張りに使おうとすると、釘を細い幅の中に…手打ちで一直線に打たなければならなくなるので、トンカチなどの扱いに慣れていない生徒さんにはとても困難な作業になるのです。
それに…機械製の張りキャンに使われる『ファルカタ ( = 南洋桐) 材』は、とても軟らかいのでへこみや歪みが生じやすく、磨耗に対する剛性も全然ありません。
機械を使って布を全体的に伸ばしてから “釘打ち機” という専用の機械で1列分の釘を “一斉に打つ” という…張りキャンバス工場での作業であれば軟らかいファルカタ材の木枠でも全然問題は無いんですが、手張り作業でみなさんが使う “キャンバスプライヤー” のように一点だけに力がかかるような引っ張り方に対する対摩耗性は…ファルカタ材は持ち合わせておりません。
硬いベイスギ材の木枠に比べるとはるかはるかにに弱いのです。

ですから、機械製の張りキャンの木枠の再利用だけでなく、手張り用に売られているファルカタ木枠の複数回の使い回しも避けてください。
つまり、ファルカタ材の木枠を使って手張りするのなら、新品をもちいての1回っ切り!!!
ベイスギのように複数回の使用には耐えられません。

ファルカタ木枠を2回とか3回使うのって、使用済みの紅茶のティーバッグを干して何度も使うようなものですよ。
そんな『うすいさちよ28歳独身さま』のような事を生徒さんに強いるのは…大変失礼です!!!!
要するに…複数回の張り替えを予定されているのなら、ベイスギ材の木枠が必須になるわけです。
このへんのことは、3ダースメルマガの読者様ならとっくにご理解いただけていることでしょう。
ただし、ベイスギ木枠とて無限に使えるわけはありません。5年 (5回) あたりが耐用年数だと思います。
耐用年数を過ぎていそうな木枠は処分するしか方法はありません。0円で部員さんに払い下げるのも一つの方法でしょう。
読者のみなさん、点検・管理が不十分で木枠の使用年数がわからない…なんてことになってませんか?
部長か、部の会計さんが責任もって備品の管理をする体制を作れていますか?
木枠の耐用年数を見極められないようなら…正直言って手張りを指導する資格なんか有りません。ベイスギ木枠での手張りは潔く諦めましょう。
生徒さんがかわいそうですから…。
前回のメルマガに対して次のようなご感想が届きました。
『たしかに3ダースサンが書いたグラフのラインは美しいですね。しかし、その例えに使ってらした1万2千円の木枠って、高すぎませんか? 一体、どの大きさの木枠の事なんですか? 全然ピンと来ないんですが…』と。
ええ、そうでしょう。高いですよねぇ。
ピンと来ませんでしたか。あぁ、そうですか…。

前回のメルマガで例に挙げた12,000円っていうのは…画用木枠のトップメーカー『マルオカ』さんのベイスギ木枠F50を想定して書きました。
現在の税込み定価が15,400円なんです。
2割引きすると12,320円です。
ちなみに4年前 (2019年) の4月の時点では、木枠の値段も安かったし消費税も8%だったため、同じモノが2割引きで9,300円程度でした。
『トップメーカーのは、そりゃあ高いでしょう。使うのは高校生なんだからもっと安い木枠でいいんです !』って思われるかもしれませんが、国内メーカーによるベイスギ木枠の価格設定は横並びですよ。
なぜなら、国内メーカー製のベイスギ木枠の9割は長野県木曽郡木祖村での製造なんですよ。
現在、木祖村で3社が木枠を作ってますね。共同体意識が強く、村全体が親戚のような地域でもあります。今は違いますが、30年前は祭りの時期になるとみんなが1週間仕事を休んじゃう…って感じの地域。
ですから、ベイスギ材のF50の税込み定価って言ったら一律15,400円なんです。
まあ、手で触っただけでトゲが刺さる○○○製の安い木枠が欲しいなら、どうぞ世○堂さんから買ってください。あれほど木材加工が粗悪なら、安いのもうなずけますわ。
また○○○製木枠は、我々…まともな画材業界人から見たら “有り得ない形状” をしているんですよ。正直、あんなのを使うヒトの気が知れません。学生時代にあんな木枠を使っていたヒトが教員になって教える立場になったら…って考えると、色々心配です。
教員になろうとしている学生さんは、良いものと悪いものの見分けが出来る人であってほしい。
っていうか、良いものと悪いものの見分けが出来ないような人は、教員になっちゃダメだと思いますよ。
(ただ、教員になってから善き画材業者の助言を聞き入れて、良いものと悪いものを見分ける能力を身に付けられた先生は、その限りではありません)
まぁ、まともな優良メーカーが作ったベイスギ木枠は、触っただけでトゲが刺さるなんてことはありませんからね。
『ウッドショック』!!
この…木枠の急激な値上がりは『ウッドショック』と呼ばれる現象です。
40代以上の先生なら『オイルショック』という言葉をご存知でしょう。
オイルショックとは、1970年代に中東情勢の悪化に伴い石油価格が急上昇し…世界の経済が混乱したことを指します。

新型コロナウィルスの感染拡大により、北米西海岸の林業現場の労働従事者の絶対量が減り…製材所も休業。木材供給量が低下したため木材価格が急上昇。
その後…北米での木材需要が急拡大したため日本への木材輸出が止まってしまい、日本国内での木材価格の上昇および木材不足が起きているのです。
なお、先程から頻繁に名前が登場する “ベイスギ” ですが、実は…『杉』じゃあないんですよ。
これ、画材業界人も…ほとんどの人がわかってません。
杉なら国内にたっくさんありますよね?
実際、杉という植物は日本列島くらいにしか存在しないそうです。
(中国の一部・台湾・朝鮮半島にも杉は分布しているようですが、台湾と朝鮮半島の杉は戦前に日本人が植林したもののようです)
『レバノンスギ』や『ヒマラヤスギ』って名前もよく聞きますが、それらは杉とは異なる…まったくの別種だそうです。
木枠に使われる『ベイスギ』も、まったく杉の仲間なんかじゃなく、ヒノキにだいぶ近い木だそうです。

杉が国内に有るんなら杉を使えばいいじゃん…と思われるみなさん、もう少々お待ちください。
早ければ半年か…1~2年くらいすると、いよいよ国内産の杉製木枠が出て来るかと思います。
実は30年以上前に、国産杉によるキャンバス用木枠が作られたことがありました。
しかし、特殊な事象が起こり得るとの事が判明し、長らく製造されていませんでした。
杉の品種改良により、ようやく製造再開のメドが立ったようです。
※国産杉による木枠の製造再開は、杉の品種改良によるものではあり
ませんでした。 製材時に施す特殊な加工により、以前に生じた不具合を抑え込むこ
とに成功したようです。
さて、学校現場でキャンバスの手張りをする上で、乗り越えなければならない二つの大きな壁があります。
まず第一の壁。木枠の壁です。
はい…。
今、ベイスギ材の木枠が全然ありません…。
品不足です。
前述の通り、ウッドショックの影響は木材価格の上昇だけでなく、根本的な品不足に陥っています。
現在、画材問屋の倉庫も…ベイスギ木枠の置場は空っぽです。メーカーから荷物が来ないんです。
メーカーも、原材料が入ってこないので、製造が出来ません。
当店も去年の11月アタマに画材問屋さんにマルオカ製の木枠…F120で4本・F150を2本・F200は5本の発注をしたのですが、5月25日にようやくF150とF200が入荷。
しかし、いまだF120は入荷日未定…とのこと。
メーカーの在庫状況は…軒並みゼロかマイナスです。
ゼロは在庫無し。マイナスは在庫が無いにも関わらず注文は受けているため『注残』 (未出荷) の数です。
6月19日現在のメーカー在庫は…F8が -323、SMが -471、F4が -566だそうです。
プラス (在庫あり) だったのはF25とF30くらい。
しかしそれらも1ケタの数でしたから、もうすでにゼロかマイナスに転じているかも…。
前回のメルマガを読まれて…新しくベイスギ木枠を買おうかと思われた先生には大変申し訳ないのですが、そういう現状なので…ご納得ください。
ですので、我々画材店がみなさんに手張り用に供給出来る木枠は…ファルカタ材のみになります。
つまり、木枠を何度も何度も何度も何度も何度も使って一回あたりの値段を下げる…という目的には合致しませんので、あしからず。
3ダースも毎年F130やF150の手張りをしていますから、正直…ベイスギからファルカタへの転換にはものすごく抵抗があります。
ファルカタだと、1回プライヤーを引くごとに木枠のエッジが布の裏面に強くコスられ、削られていくんですから…
でも、ベイスギの輸入のメドが立たないのなら…国産杉の発売まではファルカタで凌ぐしかないのです。

ベイスギ木枠を部が所有し、部員さんがどんなに素晴らしい絵を描いたとしても…その絵を木枠から剥がさせ、木枠の返却を迫る…という “悪習” から脱却するチャンスです。
今後は、生徒さんが個人でファルカタ木枠を所有し、部費で買ったロールキャンから切り出した布を張るんです。
当然、木枠の購入代金は生徒さんの負担になるでしょう (部費から一定額か一定の率で補助をするのも良いかもしれません) 。
でも、生徒さんが既製品の張りキャンをまるまる買うより…ファルカタの木枠だけだったら安く済むはずです。
そして…ベイスギ木枠を使い回していた頃とは違い、描かれた作品は…剥がされることなく、張られたままで自宅へ持ち帰れます。
学校現場でも、メンテナンス (管理・点検) 能力ゼロの美術部員さんには難しすぎた “備品の管理” から部員さんを解き放ち、部員のみなさんは自分のキャンバスをしっかり張ることに注力できます。
毎回新品の木枠にキャンバスを張るのは手間でしょうから、時には機械製の張りキャンを購入するのもよいでしょう。
でも、年に1度は個人で木枠を買って…渾身の大作を、自らの手で張ったキャンバスに描く…という、美術部員ならぜひ経験しておきたい貴重な体験を実践していただきたい。

ベイスギの木枠を使い回していた頃には顧問の先生も気づけなかった様々なコスト…『絵を剥がさなければならないという生徒さんの屈辱』『キャンバスを巻いて持って帰るという、絵の命の抹殺 (誰一人として外巻きをご存知なかったですよね?) 』『木枠無しの状態で親御さんに見ていただくという不条理』『結局、自宅では飾れないという絶望』『部活動の成果をゴミ箱に捨てなければならないという悲しみ』『運よく最寄りの画材店で新しい木枠に張り直してもらえたにせよ、その予想外の出費』『額装が叶ったとしても、巻いてしまったがための画面のヒビ割れを…毎日眺めなければならない無念』。

この感情を金銭に換算したらいくらになるのかなぁ?
ね?
ベイスギが品切れ状態なことを幸いとし、これからは生徒さん個人の購入 (重ねて申し上げますが、部費からの補助をしてもいいと思いますよ。上記『』内に書いた様々なコストを金銭化するより、はるかに安いはず) に切り替え、時には機械製の張りキャンも取り入れながら、有意義なキャンバス張り体験をさせていただきたいです。
そしてもう1つの壁のハナシは次回。
【第39回終わり】