はじめに – 尊敬する先輩格K氏
画材業界内に、3ダースがとても尊敬している先輩格の人がいます。
仮にK氏…としておきましょうか。
豊富な画材の知識を持つ人で、3ダースの一番の相談相手でもあります。
ちなみに…業界内と言いましたが、もちろん小売業の人ではありません。
しかし、画家や美術教員との直接の付き合いもあり、大サイズのキャンバス張りの経験も有る人。
そして、業界の裏バナシやメーカーの歴史などにもやたらと詳しい…
メルマガにも登場済み
あ、そういえばこのメルマガにも一度登場させてます。その時には名前や立場は明かさなかったけど…。
第16回の【またまた『#』のハナシ】で、紙ヤスリなどの「砥粒」の大きさを表す『# = メッシュ』の説明の中で、『荒い砥粒と細かい砥粒の表示方法は異なるはずだ』との見解を示してくれたのがK氏です。
(ただ、3ダースがこのハナシをK氏から聞いたのは10年以上前だったと思います。メルマガのために『#』の事を調べていたら『JIS規格R6010』という項目に辿り着き、K氏が過去に言っていたことが正しかったことが証明され、改めて彼の知識の深さにビックリしました)
対話の前提
そんなK氏と3ダースが、もう17~8年前に話したことを思い出しながら書いてみます。
もちろん一言一句正確に覚えているはずもなく、大部分は創作によって記憶を穴埋めしておりますが、みなさんにも参考になることがあるかもしれませんのでご紹介します。
なお、対話の中に登場する『社長』とは、ウチの店の先代の社長。2003年に亡くなりました。
あ、3ダースの父ではありませんよ。3ダースの父親の職業は農業で、2002年に他界しております。
K氏との対話
大サイズキャンバスの注文
K氏『3ダースさん、社長亡くなって何年か経つけど、今も…でかいキャンバスの注文は受けてるの?』
3ダース『ええ。150号は毎年複数枚、過去には200号も数枚張ってました』
K氏『社長生きてた頃は全部社長一人でやってたからねぇ。あの頃は200も毎年複数枚だったよね?』
3ダース『ええ。でも200号は画家が描くのをやめちゃったり亡くなっちゃったりで…』
K氏『3ダースさんがキャンバス張るようになったのは社長亡くなってから?』
3ダース『80号や100号は以前から張ってましたけど、120号以上は全部社長がやっちゃってたんで…💦』
K氏『あの人、張るの好きだったよねぇ。なんか俺も見たけど、社長…特殊な張り方してたよね』
3ダース『あれは真似できないっす。アタシは普通に、じっくり時間かけてやってます』
張り器について
K氏『張り器(プライヤー)は社長のを使ってるの?』
3ダース『アレはすごく変なクセがついてたから、使ってません。布をくわえる所も滑るし…。だから自分用のを買いました。布をくわえる所はゴムで、交換式のヤツ』
K氏『じゃあ200もそれで張ったんだ?』
3ダース『もちろん。社長のよりテコの足(支点)の高さがあるから、アタシには使いやすいっす』
200号を張った経験
K氏『なるほどね。200張ってみてどうだった?』
3ダース『ええ。パンッパンに張れましたよ。最初は角付近にシワが出たんですが…』
K氏『ん? で、どうしたの?』
3ダース『その日はどうやってもシワが消せなかったんで2日くらいしてから引っ張り直したんですよ、タックス何本か抜いて…』
K氏『ほう』
3ダース『そしたら、どうやっても消えなかったシワが、キレイさっぱり』
K氏『ははは、そんなもんだよ。慌てずに、2~3日置いてからやれば、あっけないくらい簡単に直るよね』
150号の硬い布
3ダース『150号のお客さんの指定する荒目の布が、硬くてなかなか伸びないんっすよ』
※この画家が、現在130にサイズダウンして同じ硬い布を指定して来ます。
K氏『(苦笑い)』
3ダース『張る時期が11月頭だからまったく伸びなくて…。何日かかけて引っ張り直しをしてます』
K氏『部分的に?』
3ダース『いや、部分じゃどうにもならないから、タックス抜いては布を引っ張って…また打って、をぐるりと一周』
K氏『で、完璧に張れてる?』
3ダース『完全に完璧!』
プロとしての仕事
K氏『なら、それでいいんじゃん? 一発で張り上げて…その日には張れてるような音がしてても、いざ納品する時にボヨンボヨンじゃ結局不良品を納品することになるもんね。3ダースさんはプロなんだから胸張って納品出来るものを作らなきゃダメだよ。「完全に完璧」って言えれば立派。画家は自分じゃ張りもしないクセに、張りが少しでも弱いと文句言うからね』
社長の張り方
3ダース『大きな声じゃ言えないんすけど、昔…社長が張った200号、何日かしたら少し張りが弱まってたことありましたわ💦』
K氏『あの人、一発で済ませたがるから…張り直しってやりたがらないんだよね。釘穴が2列になるのを嫌がるんだよ。たしかにあの張り方だと一発でけっこう強くイけるんだけど…さすがに200の面積だとユルむ可能性はあるよね。だから、3ダースさんみたいに何日もかけるつもりで臨むのが本来の正しい姿じゃないかな。釘穴が余計に空いちゃうことを恥じるんじゃなく、張り直そうとしないことを恥じるべき』
側面の釘穴
3ダース『でもキャンバスの側面に穴がたくさん空いてるのは、やっぱカッコ悪い…』
K氏『(笑)そんなもん、モデペやジェッソで埋めちゃえばいいじゃん。大事なのはオモテ面で、側面の見映えなんかどうでもいいんだから』
3ダース『あ、埋めちゃって いいんっすね? 実はもう…何度もソレやっちゃってます』
K氏『(笑)…布を剥がして木枠を使い回すヒトだと布の穴を埋めちゃった事がバレるだろうけど、だいたい画家は木枠の使い回しはしないでしょ?』
木枠の使い回し
3ダース『ええ、150号の人達は毎年木枠と布を注文してくれます。でも120号の画家と100号以下のアマチュア画家は…木枠は使い回しで、毎年張り替えです』
K氏『うわぁ、画家でも使い回すかぁ…。その使い回すヒト達って、自分で古いキャンバス剥がして木枠だけを店に持ち込む感じ?』
3ダース『いや、持ち込むっていうか…ウチが木枠を取りに行く感じっすけど…。中には「古い画面は処分しちゃって」って、前回の作品が張ってあるまま預けてくるアマチュアのヒトもいます』
K氏『剥がしもしないのかよぉ? しかも、処分してくれ…ってのは嫌だよねぇ。昔の絵とはいえ、「作品」なんだし…』
3ダース『だから、剥がした絵も新しいキャンバス張って届ける時に一緒に返しますよ』
K氏『けっこう雑用引き受けちゃってるねぇ。お気の毒さま…。ところで、木枠の使い回しは何回くらい許容してるの』
木枠は何回使えるのか?
3ダース『う~ん、こっちからは「そろそろ新しい木枠に替えましょう」ってなかなか言いづらいんっすよね。だから「コレ、何年モノですか?」って驚くくらい古い木枠に張ることも…。ところで逆にうかがいますが、木枠って何回くらい使えるんっすかね?』
K氏『絵を描く本人が自分でキャンバスを張るんだったら、そりゃ自己責任で何回でも好きなだけ張ればいいよ。でも3ダースさんは商売で張ってるんだからさぁ、傷みきった木枠なんかに張ったキャンバスを納品して…まともにお金取れるかい?…プロとして』
3ダース『…』
商品として納品できるか
K氏『だから、強度的に保証出来るか出来ないか…って小難しいハナシじゃなく、**商品として前回より劣った状態にしか仕上がらないんなら、同じお金はもらえないんだよ。**かといって毎年値下げを続けるってのも商売として非現実的でしょ? だからどこかで区切らなきゃ』
3ダース『でもお客さんって、木枠は何度でも何度でも使えるって思ってるから…』
たとえ話:タイヤの使い回し
K氏『じゃあたとえバナシだけどさ…車買い換えるとするじゃん? そん時、カーディーラーの営業マンに「新車はタイヤ無しで納車してよ。今のクルマから外したタイヤ付けるからさ。ちなみにそのタイヤ、親のクルマから受け継いだんだ。親はじいさんのクルマから受け継いだんだ」なんて言ったら、ディーラーの営業マンどう思う?』
3ダース『いや、どうもこうも…。「あんたらどんだけケチな一族だよ」って突っ込むかな? それにしてもタイヤはそんなに長く使えませんよ。1台の車でも2回くらいは交換するのが普通だし…。タイヤは消耗品ですからね』
K氏『も!』
※この『も!』の意味、最初はわかりませんでした。どうやら3ダースが『タイヤ「は」』と言ったのを『消耗品はタイヤだけじゃないぞ、他にもあるだろ』ってK氏が言ってるように思ってしまいました。
木枠も消耗品
3ダース『も? あ、「も?」…そっか、タイヤ「も」ワイパーブレード「も」オイル「も」消耗品だから交換必要ですね』
K氏『(苦笑い)いや、俺が言いたかったのは「ワイパー」や「オイル」の事じゃなく…』
3ダース『あ、待って待って! 「も」だ。「も」。タイヤ「も」、木枠「も」消耗品だ。そうっすよね?』
K氏『そ。タイヤと同じく、**木枠「も」消耗品。いや、木枠「こそ」消耗品だよ。**100号なら一回で60…いや7~80個かな? それくらいの釘穴が木枠に空くんだし、張り具合の調整とかをしてれば釘穴はもっと増えるでしょ? 木枠裏面の「張り器の跡」も同じだけ付くんだし、強く張ってりゃテコの足が木にめり込むから、トゲやササクレだってけっこう出来る。木枠って相当「消耗」してるんだよ』
エッジの磨耗
3ダース『ん~、でもそれは仕方ないんじゃ?』
K氏『まあ、側面や裏面は仕方ないよ。でも一番磨耗するのはエッジだよ。一番大事なエッジが毎回傷むんだよ』
3ダース『あ、「エッジ」って正面と側面のキワの所ですよね?』
K氏『そ。3ダースさんみたいにオーソドックスな張り方なら、キャンバス布の裏面を木枠のエッジにこすり付けながら張ってると思う…。布の裏のざらついた面で、けっこうな力を加えて木枠のカドをこするワケでしょ? まるで紙ヤスリかけるみたいにさぁ…。あれ、布を剥がすと木枠のエッジがスレてへこんでたり…木の繊維がバラけてささくれたりしてるんだよ』
3ダース『ああ、わかります。硬い布で張る時はエッジがくぼむくらいに引っ張らないと、強い張りになりませんからねぇ』
エッジのへこみは修復不可能
K氏『そ。強く張れば特にエッジがへこむ。**その木枠のへこみを直すのは不可能だよ。**それなのに「何度も何度も同じ状態に張れます」なんて言えないでしょ? 釘穴だって、木枠の同じ穴にタックスが入っちゃったら、そのタックスの「効き」は2割以下じゃない? そんな張り方で出来上がったキャンバスは、良品か?…不良品か?』
3ダース『………』
製造物責任
K氏『ほとんど効いてないタックスがキャンバスからスルッと抜け落ちました。お客さんがアトリエ内でそれを踏んで怪我をしました。誰に責任が有る?』
3ダース『う~ん』
K氏『「製造物責任法」って法律もあるし…ね』
3ダース『まぁ、タックスに関しては…トンカチで打った時に手応え無く…前の穴に入っちゃったようなヤツはすぐ抜いて、近くに打ち直すようにはしてましたケド…』
K氏『お、さすがだね。でも同じ人が3回も4回も張るんだとしたら、やっぱりタックスはいっつも同じ場所に打つようになるよね?』
釘穴のメンテナンス
3ダース『ええ。アタシはどうしてもそれが嫌で嫌で…。複数回張り替えなきゃならない場合は、釘穴をパテとかボンドで埋めてから作業しましたよ。さっき言った120号の画家のキャンバスを張る時は毎回っす』
K氏『偉いねぇ。社長はそんなことしてなかったでしょ?』
3ダース『社長はそういう手間をかけることはしませんでしたね。前と同じ穴にタックスが入っても気にしないし…。でも今は、張り替え含めて…キャンバス張りは全部アタシがやるようになったんで、やっぱ効率良く仕事をしたいんっすよ。同じ穴に入るたびにタックス打ち直すより、事前に全部の穴を埋めておけば…張る時には余計なストレス無く張れますからね』
木枠の寿命
K氏『だからね、杉材(ベイスギのこと)の木枠でも、**使い回しは2回までだよ。**つまり、新品のキャンバスを作った時が1回目…それを剥がして次の布を張ったら2回目。それで終わり。その次の張り替えの依頼は断る!』
3ダース『え? 寿命…短か過ぎじゃないっすか?』
K氏『いや、俺は2回が適正だと思うよ。仮に、パテやボンドで釘穴を埋めたりササクレを処理したり…ちゃ~んとしたメンテナンスを毎回毎回張る前にやっていれば、4回くらいは張れるかなぁ。あ…でも、エッジの磨耗は直せないんだからエッジの視点から見たら4回はキツいか…』
3ダース『いや、お客さんは「木枠は無限に使える」って考えてるから納得しないっすよ』
K氏『メンテナンスもしないで3回も4回も使えるわけ無いじゃん!』
メンテナンスは誰がやるのか
3ダース『お言葉ですが、100号や120号…1枚分の釘穴埋めるだけで大仕事ですよ。けっこう時間もかかるし』
K氏『だ~か~ら~、3ダースさん…勘違いしてない? 木枠の持ち主はお客さんでしょ? だからメンテナンスはお客さんが自分でやるんだよ! それが出来ないなら…つまり、お客さんがメンテナンスしてくれないんなら、「もう1回張ったら終わりですよ!」ってお客さんに言えばいい。お客さんを教育するのも画材店店主の仕事だよ』
3ダース『…教育っすか』
品質を劣化させない
K氏『じゃあ、メンテナンスを全部3ダースさんが引き受ける? 張り賃…相当もらわないと合わないぜ? あ、あとタックスは1回使ったら終わりだよ。お客さんの所から「剥がしたタックス」が戻って来ても使っちゃダメだよ。どれも先が鈍ってるだろうし、錆びてたり絵具で汚れてたりするからね。3ダースさんはあくまでも「商品」を作ってるんだから。品質は劣化させないようにね』
K氏の教え
とまあ、なかなか『製造物責任』とか『良品・不良品』とか『企業倫理』とかに厳しいK氏でしたが、おっしゃることはどれもごもっともなハナシ…。
K氏の教え まとめ
- 『ベイスギ木枠とはいえ、無限に使える訳ではない』
- 『木枠のエッジ部分のへこみやすり減りは防げないし、修復できない』
- 『画材店が「商品」として張る場合は、ベイスギ木枠の使い回しは2回まで』
- 『2回以上の使い回しを希望するなら、木枠の持ち主本人が責任を持ってメンテナンスをすべき』
- 『そして、画材店店主はお客さんの教育にも責任を持つべき』
いやぁ、さすが。
今思い出しても惚れ惚れするお言葉!
K氏、厳しいようですが愛がありますよ。深い愛が!!!!
- お客さんに対する愛
- 画材店に対する愛
- 画材業界に対する愛
- キャンバスに対する愛
- 木枠に対する愛
- タックスに対する愛
誰かが怪我をしないように…。
誰かが嫌な思いをしないように…。
画材店が無理なサービスを強要されないように…。
木枠が無限に使えると思っているヒトの目を覚まさせる、知識と経験。そして説得力!
3ダースはその1割くらいは受け継げてるかなぁ。
どうかなぁ?
当店の独自ルール
その後…当店では独自ルールとして、画家の先生もアマチュア画家の人も…木枠の使い回しは2回に限るようにしました。
そして、それを受け入れてくれる方には、2回目を張る前に3ダースがサービスでメンテナンスをするようにしています。
『もし、3回以上の使い回しをなさりたいなら、最初からご自身で木枠のメンテナンスを…』ってお客さんに申し上げたら、ほとんどのお客さんは『機械製の安い張りキャンでいいや』っておっしゃいました。
実際、張りキャンが一番安いんです。手間とか含めて考えたら…。
学校への補足
今回のハナシは、3ダースが作り上げる『商品』としてのキャンバスの手張りのこと…。
学校での木枠の使い回しを2回に限れ…なんて言ってるわけではありません。
K氏も言ってました。
絵を描く本人が自分でキャンバスを張るんだったら、そりゃ自己責任で何回でも好きなだけ張ればいいんですよ。
それに高校生の手張りだったら張る力もそれほど強くないでしょうから、木枠のエッジが傷むことも少ないでしょう。
美術部の責任
ただ、木枠の持ち主は学校の『美術部』。
「美術部という組織」が主体的になって、共用の道具や備品の管理・メンテナンスをする責任があります。
つまり、顧問や部員が動かなければ、何も成し遂げられません。
積極的にメンテナンスなどをしましょうね。
メンテナンスもしないクセに手張りだけをするんだとしたら、そりゃおかしいです!
K氏のもうひとつのハナシ
じゃあ最後にもうひとつK氏のハナシですが、K氏…クルマのエンジンを焼き付けて廃車にしたことがあるそうな。
あの人、自家用車はマメに手入れをして…オイルも高いのとか使ってたそうなんですが、**仕事に使ってた車の手入れはけっこうサボってたみたい。**オイル交換も放ったらかしにしてたら、ある日突然エンジンが止まったと…。
走ってる途中でエンジンもラジオも完全に止まって、たしかハザードランプは点いたのかな? 惰性で進むクルマを左に寄せて停めたみたい。
で、ディーラーの営業マンに電話したら『JAFを呼べ』と…。JAFに電話したら『レッカー車が到着する前に警察に電話して、安全な場所まで車を押してもらえ』って。で、110番にかけてパトカー呼んで、複数の警察官に車を押してもらったとか…。
どこかの橋を渡る手前だったらしく、交通に大きな迷惑をかけることは無かったそうな…。
故障の原因
故障の原因は…オイルの劣化と量の不足による潤滑不足で、シリンダー内壁にピストンが癒着して止まっちゃったそうな。
車はやむなく買い替え…。
『メンテナンスって大事だよなぁ~』っておっしゃってました。
メンテナンスとは
メンテナンスとは…『整備・維持・保全・保守・点検・手入れ・修理・修繕・交換』などの言葉に言い換える事ができると思います。
みなさん、木枠やタックスに限らず…仮縁とかネジとか様々な物の普段の『点検』、出来てますか?
木枠の修理・修繕どころか…普段の点検すらしていない美術部は、キャンバスの手張りなんかする資格無しですよ。
K氏の振り返り
K氏の使ってた車は、実際には廃車でなく、ディーラーのサービスマンがエンジンをバラして修理し、中古車として販売したそうな。
後日にそれをディーラーから聞いたK氏は『自分でやれるメンテナンスさえマメにしていれば、車を買い替えずに済んだ。ディーラーは「修理」という高いレベルのメンテナンス能力があったから廃車寸前の車を「商品」として売ることができた』と、振り返ってらっしゃいました。
最後の最後まで『メンテナンス・商品・流通』で物事を考えてらっしゃる。
K氏、考察が深い!
【第25回終わり】













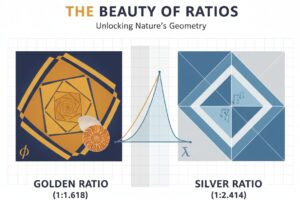



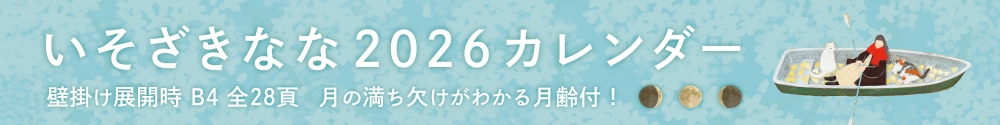





コメントを残す